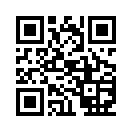いま帰宅中
2010年12月31日
主人のおうちで紅白を見て、花札を楽しんで、いまから一時間かけて名瀬の自宅に戻ります。
明日は主人のおうちでお正月!
秋介さんからお電話。すさまじくいいお話。しかし残念だが今は話せない。すごくデリケートな内容なので。
あー、話したい!
では、みなさん、よいお年を!
明日は主人のおうちでお正月!
秋介さんからお電話。すさまじくいいお話。しかし残念だが今は話せない。すごくデリケートな内容なので。
あー、話したい!
では、みなさん、よいお年を!
Posted by アマミちゃん(野崎りの) at
23:13
│Comments(3)
『誰が、世界とバーナンキを救ったのか?』(ヘラトリ)
2010年12月31日
説明不要ですね。
当時、麻生首相が大川総裁に智慧を求めたのは事実ですから。
これからゆっくりと、幸福実現党の提言している政策をあちこちが公然とパクりはじめるでしょうね。
_________
『世界の目を醒ます
ヘラトリ・トピックス』
(第14号)
『誰が、世界とバーナンキを
救ったのか?』
今回の文章は、英語版サイトの方にアップしました。(vol.2です。)
正式タイトルは、
"Who Saved Bernanke and Who Saved the World?"
です。
一昨年秋、大川総裁が麻生首相(当時)にアドバイスして、IMFに10兆円拠出させ、それによって、事実上「世界恐慌」を止めた事実は、世界にほとんど知られていないので、
これを広く世界の人々に知っていただくべく、今回のヘラトリ・コラムは、英文で発表しました。
全訳(和訳)をこちらに掲載すると、膨大な量になってしまうので、
ニューヨークのウォールストリートを意識して、専門的に隙(すき)のない文章で書いた
「リーマンショック前後の事実関係の分析」
の部分については、こちらでは割愛することとし、
専門外の方でもなじみやすい"総裁にまつわる逸話"の部分を中心に抜粋して、日本語の方ではお届けすることにします。
現在、「ヘラトリ.トピックス」日本語版サイトを再構築中であり、これが完成したら、全文(和訳)を掲載する予定です。
(今回も、斉藤潤翻訳事務所に多大なるご協力を頂きましたことに、心から謝意を表します。)
英語版サイトのURLは、以下のとおりですので、是非、ご覧ください。
http://heratri-topics.blogspot.com/
以下の日本語は、英訳用にやや翻訳調になっている点、ご容赦ください。
なお、バーナンキとは、現アメリカ連邦準備理事会議長(日本では日銀総裁に当たる)です。
『誰が、世界とバーナンキを救ったのか?』(抜粋)
2008年10月、世界経済は、間違いなく、がけっぷちに立っていた。前月の9月には、アメリカのリーマン・ブラザーズが破綻し、AIGが巨額の政府資金投入によって救済され、その土壇場の「国有化」で、世界経済は、何とか堤防の決壊を免れた。
ベン・バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長も、
「10月は本当に危なかった。大恐慌再来の寸前まで行っていた」
と、後日のインタビューで述べている。
誰もが1931年9月の悪夢〜イギリス・ポンドの金本位制離脱(今で言えば大暴落)とそれに続く10年の大不況〜を思い浮かべた。
しかし、悪夢は起きなかった。それは、一部の人々(バーナンキとそのチームのメンバー)の献身的努力と幾分かの幸運の賜物であると、誰もが思った。確かにそれは、一部当たっている。
しかし、真実を言えば、ある一人の男が、堤防を最後の決壊から守ったのだ。世界の大半の人々は、その事実とその人の存在を知らない。
真相を知る私のような人間から見ると、その様子は、あたかも、中国の故事に出てくる"墨子"の姿を思い起こさせる。
あるとき、墨子の祖国が、隣国との戦争の危機に見舞われた。実際に開戦となれば、彼の祖国に勝ち目はないように思われた。
彼は、祖国の王でも宰相でもなく、いわんや、何の権限も責任も有していない一人の知識人にすぎなかったが、誰から頼まれるでもなく、誰一人に知られることもなく、彼は、単独で、敵国に乗り込み、厳しい交渉を乗り切って、祖国を滅亡の危機から救った。
やがて、国境の町まで戻った墨子の姿を見た祖国のある農民は、
「ふん、おいぼれ爺(じじい)め」
と、彼のことを鼻でせせら笑ったが、しかしその農民は、「そのおいぼれ爺こそが、彼の家族の命と財産を守った」ことなど、知るよしもない。そして、昨日までがそうであったように、明日もまた、平和な日々が続いていったのだ…。
弾を撃ち尽くしていたバーナンキ
(この節省略)
1931年の悲劇の本当の原因
(この節省略)
太平洋の反対側で、"救世主"が動く
そのとき、事態の推移を太平洋の対岸から、じっと見つめている男がいた。というか、彼は、リーマン・ショックが起きた瞬間に、コトの本質を理解した。
「おそらく、アメリカもヨーロッパも、自分の国以外には手が回るまい」
そう見抜いた"救世主"は、かつての中国の墨子のように、迅速に動き出した。日本政府の麻生太郎首相(当時)に連絡を取った"救世主"は、
「米・欧は手が回らない新興国の金融危機を未然に防ぐために、日本は大至急、大胆な資金の拠出をせよ」
とアドバイスした。
この決断がもたらす絶大な効果も、そして、今起きている事態の重大な深刻さも、おそらくは十分に理解していなかった麻生首相ではあったが、マスター大川のアドバイスだということで、とにもかくにも、首相は頑張った。
その実行面の責任者であった財務省の国際局長〜彼は「国際金融市場を司る司祭達」=「国際通貨マフィア」の一員で、世界の仲間達からは、"次期財務官殿(通貨マフィアの日本代表)と呼ばれていた〜が、大川隆法幸福の科学総裁の東大法学部のクラスメイトであったことも、幸いしたことだろう。
(勿論、大川総裁は、彼とは連絡を取っていない。しかし、大学のゼミの議論で大川総裁に歯が立たなかった彼は、マスター大川の"指示"(instruction)の持つ重みが、極めてよくわかるタイプの一人だったことだろう。)
日本政府は迅速に行動し、新興国の金融危機を回避する手段として、IMFに1,000億ドル(約10兆円)拠出することを決定した。
これが一瞬で、世界の金融システムに安心感をもたらし、事実上、「世界恐慌」を回避したことは、この日本政府の決定に対するIMFストロスカーン(Strauss-Kahn)専務理事の"手放しの歓迎声明"を見れば、よくわかるだろう。
私の見るところ、これは、戦後の日本の歴史の中で、最も劇的で主導権の発揮された〜言葉を換えれば、最も日本人離れした〜国際貢献の一つであり、外交の一つである。しかし、世界の大半の人は、この救世主〜現代の墨子〜の存在を知らない。
次の一手
日本国内の事情に詳しい方ならご存知だろうが、救世主は、鳩山前首相の反米思考を、約半年かけて修正させ、日米関係を破綻の淵から救った。
菅直人現首相に対しても、その就任後には、(彼の本心はともかくとして)、事実上、外交路線を保守化するように強いて、太平洋の不穏な波が、これ以上大きくならないように腐心している。
救世主はまた、アメリカ経済の苦しみについても、「何とかならないか」と、心を痛めている。日本がアメリカに手を差し伸べることによって、日・米ともに景気回復と繁栄への道に再び入れないか、その道を考えている。
その口からは、まだ具体的な「次の一手」は述べられていないが、筆者が推測するところ、
「この国全体を、中期的に円高の方向に持っていくことによって、アメリカに景気回復策(ドル安)の余地を用意してあげる」
ことが、その中には含まれているように思われる。
現代の救世主は、心の教えと来世の幸福を説くだけではない。救世主は本来、旧約聖書の中でも説かれていたとおり、現代の地上社会の諸問題を解決し、現実世界の中でも、人々を幸福にしていこうとしているのである。
●お問い合わせ・ご予約などは、電話・FAX、または
こちらのアドレスhokkaido@sj.irh.jpまでお送りください。
●メール配信をご希望の方は、「メル友希望、お名前、支部名、会員番号」をご記入の上、
hokkaido@sj.irh.jpまでメールをお送りください。
北海道正心館
Tel:011-640-7577
Fax:011-640-7578
当時、麻生首相が大川総裁に智慧を求めたのは事実ですから。
これからゆっくりと、幸福実現党の提言している政策をあちこちが公然とパクりはじめるでしょうね。
_________
『世界の目を醒ます
ヘラトリ・トピックス』
(第14号)
『誰が、世界とバーナンキを
救ったのか?』
今回の文章は、英語版サイトの方にアップしました。(vol.2です。)
正式タイトルは、
"Who Saved Bernanke and Who Saved the World?"
です。
一昨年秋、大川総裁が麻生首相(当時)にアドバイスして、IMFに10兆円拠出させ、それによって、事実上「世界恐慌」を止めた事実は、世界にほとんど知られていないので、
これを広く世界の人々に知っていただくべく、今回のヘラトリ・コラムは、英文で発表しました。
全訳(和訳)をこちらに掲載すると、膨大な量になってしまうので、
ニューヨークのウォールストリートを意識して、専門的に隙(すき)のない文章で書いた
「リーマンショック前後の事実関係の分析」
の部分については、こちらでは割愛することとし、
専門外の方でもなじみやすい"総裁にまつわる逸話"の部分を中心に抜粋して、日本語の方ではお届けすることにします。
現在、「ヘラトリ.トピックス」日本語版サイトを再構築中であり、これが完成したら、全文(和訳)を掲載する予定です。
(今回も、斉藤潤翻訳事務所に多大なるご協力を頂きましたことに、心から謝意を表します。)
英語版サイトのURLは、以下のとおりですので、是非、ご覧ください。
http://heratri-topics.blogspot.com/
以下の日本語は、英訳用にやや翻訳調になっている点、ご容赦ください。
なお、バーナンキとは、現アメリカ連邦準備理事会議長(日本では日銀総裁に当たる)です。
『誰が、世界とバーナンキを救ったのか?』(抜粋)
2008年10月、世界経済は、間違いなく、がけっぷちに立っていた。前月の9月には、アメリカのリーマン・ブラザーズが破綻し、AIGが巨額の政府資金投入によって救済され、その土壇場の「国有化」で、世界経済は、何とか堤防の決壊を免れた。
ベン・バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長も、
「10月は本当に危なかった。大恐慌再来の寸前まで行っていた」
と、後日のインタビューで述べている。
誰もが1931年9月の悪夢〜イギリス・ポンドの金本位制離脱(今で言えば大暴落)とそれに続く10年の大不況〜を思い浮かべた。
しかし、悪夢は起きなかった。それは、一部の人々(バーナンキとそのチームのメンバー)の献身的努力と幾分かの幸運の賜物であると、誰もが思った。確かにそれは、一部当たっている。
しかし、真実を言えば、ある一人の男が、堤防を最後の決壊から守ったのだ。世界の大半の人々は、その事実とその人の存在を知らない。
真相を知る私のような人間から見ると、その様子は、あたかも、中国の故事に出てくる"墨子"の姿を思い起こさせる。
あるとき、墨子の祖国が、隣国との戦争の危機に見舞われた。実際に開戦となれば、彼の祖国に勝ち目はないように思われた。
彼は、祖国の王でも宰相でもなく、いわんや、何の権限も責任も有していない一人の知識人にすぎなかったが、誰から頼まれるでもなく、誰一人に知られることもなく、彼は、単独で、敵国に乗り込み、厳しい交渉を乗り切って、祖国を滅亡の危機から救った。
やがて、国境の町まで戻った墨子の姿を見た祖国のある農民は、
「ふん、おいぼれ爺(じじい)め」
と、彼のことを鼻でせせら笑ったが、しかしその農民は、「そのおいぼれ爺こそが、彼の家族の命と財産を守った」ことなど、知るよしもない。そして、昨日までがそうであったように、明日もまた、平和な日々が続いていったのだ…。
弾を撃ち尽くしていたバーナンキ
(この節省略)
1931年の悲劇の本当の原因
(この節省略)
太平洋の反対側で、"救世主"が動く
そのとき、事態の推移を太平洋の対岸から、じっと見つめている男がいた。というか、彼は、リーマン・ショックが起きた瞬間に、コトの本質を理解した。
「おそらく、アメリカもヨーロッパも、自分の国以外には手が回るまい」
そう見抜いた"救世主"は、かつての中国の墨子のように、迅速に動き出した。日本政府の麻生太郎首相(当時)に連絡を取った"救世主"は、
「米・欧は手が回らない新興国の金融危機を未然に防ぐために、日本は大至急、大胆な資金の拠出をせよ」
とアドバイスした。
この決断がもたらす絶大な効果も、そして、今起きている事態の重大な深刻さも、おそらくは十分に理解していなかった麻生首相ではあったが、マスター大川のアドバイスだということで、とにもかくにも、首相は頑張った。
その実行面の責任者であった財務省の国際局長〜彼は「国際金融市場を司る司祭達」=「国際通貨マフィア」の一員で、世界の仲間達からは、"次期財務官殿(通貨マフィアの日本代表)と呼ばれていた〜が、大川隆法幸福の科学総裁の東大法学部のクラスメイトであったことも、幸いしたことだろう。
(勿論、大川総裁は、彼とは連絡を取っていない。しかし、大学のゼミの議論で大川総裁に歯が立たなかった彼は、マスター大川の"指示"(instruction)の持つ重みが、極めてよくわかるタイプの一人だったことだろう。)
日本政府は迅速に行動し、新興国の金融危機を回避する手段として、IMFに1,000億ドル(約10兆円)拠出することを決定した。
これが一瞬で、世界の金融システムに安心感をもたらし、事実上、「世界恐慌」を回避したことは、この日本政府の決定に対するIMFストロスカーン(Strauss-Kahn)専務理事の"手放しの歓迎声明"を見れば、よくわかるだろう。
私の見るところ、これは、戦後の日本の歴史の中で、最も劇的で主導権の発揮された〜言葉を換えれば、最も日本人離れした〜国際貢献の一つであり、外交の一つである。しかし、世界の大半の人は、この救世主〜現代の墨子〜の存在を知らない。
次の一手
日本国内の事情に詳しい方ならご存知だろうが、救世主は、鳩山前首相の反米思考を、約半年かけて修正させ、日米関係を破綻の淵から救った。
菅直人現首相に対しても、その就任後には、(彼の本心はともかくとして)、事実上、外交路線を保守化するように強いて、太平洋の不穏な波が、これ以上大きくならないように腐心している。
救世主はまた、アメリカ経済の苦しみについても、「何とかならないか」と、心を痛めている。日本がアメリカに手を差し伸べることによって、日・米ともに景気回復と繁栄への道に再び入れないか、その道を考えている。
その口からは、まだ具体的な「次の一手」は述べられていないが、筆者が推測するところ、
「この国全体を、中期的に円高の方向に持っていくことによって、アメリカに景気回復策(ドル安)の余地を用意してあげる」
ことが、その中には含まれているように思われる。
現代の救世主は、心の教えと来世の幸福を説くだけではない。救世主は本来、旧約聖書の中でも説かれていたとおり、現代の地上社会の諸問題を解決し、現実世界の中でも、人々を幸福にしていこうとしているのである。
●お問い合わせ・ご予約などは、電話・FAX、または
こちらのアドレスhokkaido@sj.irh.jpまでお送りください。
●メール配信をご希望の方は、「メル友希望、お名前、支部名、会員番号」をご記入の上、
hokkaido@sj.irh.jpまでメールをお送りください。
北海道正心館
Tel:011-640-7577
Fax:011-640-7578
おやっさん
2010年12月31日
昨夜は父が忘年会だったらしい。
7時頃飲み屋に送り、自宅に戻った。
突然携帯が鳴ったのは夜中12時でした。
「ワルい!今から迎えにきてくれー。」
「あのー。」
「あと、友達を小湊(中心部から車で15分)に送ってくれ!」
「はぁ?」
「待ってるぞ!早くしてくれ!さむー」
あわてて母に電話すると
「あんただけだと居眠りするが!私もいくから!」
と母とグーをまず乗せていく。
屋仁川(奄美市中心部の歓楽街)にいくと父と父の友人が震えながら待っている。
「おい、一番軒(ラーメン屋)にいってくれ!」
「ああん!」
ラーメン屋で父と友人は食事。
その間私と母とグーは缶コーヒーをすすりながら待つ。
屋仁川がいつもの不況はどこへやら、すさまじい賑わい。いつもこんなになってほしいなぁ。
それから父の友人を小湊に送り、そのあと帰宅。
時計みたら1時40分でした…
一年に数度のわがままだ、許してやる!
そのかわり拠点こいよ!
(`∀´)
7時頃飲み屋に送り、自宅に戻った。
突然携帯が鳴ったのは夜中12時でした。
「ワルい!今から迎えにきてくれー。」
「あのー。」
「あと、友達を小湊(中心部から車で15分)に送ってくれ!」
「はぁ?」
「待ってるぞ!早くしてくれ!さむー」
あわてて母に電話すると
「あんただけだと居眠りするが!私もいくから!」
と母とグーをまず乗せていく。
屋仁川(奄美市中心部の歓楽街)にいくと父と父の友人が震えながら待っている。
「おい、一番軒(ラーメン屋)にいってくれ!」
「ああん!」
ラーメン屋で父と友人は食事。
その間私と母とグーは缶コーヒーをすすりながら待つ。
屋仁川がいつもの不況はどこへやら、すさまじい賑わい。いつもこんなになってほしいなぁ。
それから父の友人を小湊に送り、そのあと帰宅。
時計みたら1時40分でした…
一年に数度のわがままだ、許してやる!
そのかわり拠点こいよ!
(`∀´)
Posted by アマミちゃん(野崎りの) at
10:24
│Comments(5)
エル・カンターレとの約束を思い出す(後編)
2010年12月31日
繰り返しますが、この内容は非常に重要な悟りのエッセンスがつめこまれてます。
どうか、繰り返し読んでください。
この内容を学ぶこむだけで、二つ以上の研修でいただく学びの深さがあると思います。
(特にひっかかったキーワードはノートに書いてそのテーマで深く思慧されることをオススメ!)
実はその意味で、この講話自体が一つの「禊ぎ」になってるんですよね。
さすが、年末にふさわしいご講話です。小林館長、おそるべし!!!!!
__________
(前編よりつづき)
入念な準備をした上で
多くの霊人も仰っておられますけれども、主エル・カンターレ本仏はひたすら大きいので、例えばその大きさは、
「釈迦とキリストの悟りが手のひらに乗って見えた」
と『フランクリー・スピーキング』にありました。この前の「韓信の霊言」によれば、
「仏陀の時と違って、主エル・カンターレを支えるには、脇士としてみたら、普賢菩薩みたいな方が100人位いないと担ぎ上げられません」
とありました。
それだけ巨大な方を信仰するということは、何を意味しているかというと、
「その百倍巨大な主の願いを実現することに命を賭けます」
ということを、表面上の言葉ではなく、他人向けのプレゼンテーションとしてではなく、それを本心から「誓い」、「帰依する」ということに他ならないのです。
つまり、「私達の目標が、本当は100倍あったのだ」ということを受け止めて、制約された"自我意識"がささやく、
「出来るわけないよ」
という言葉に打ち克っていくことが、必要なのです。
そのための入念な準備が、まさに第一則から第三則にあたるわけですが、北海道正心館版は、さらに工夫を凝らして、第4則の入り方に万全を期しました。
三次元の制約というのは大きいですので、その中でこれをしっかりと掴んでいくために、第一則では、「肉体の殻を脱ぎ捨てる」ことを、まず瞑想でやります。
この世的な経歴、性別、両親、家庭環境など、いわゆる「言い訳」の材料から自由になることです。
そして、肉体意識から自由になった心を、「一念三千」ではありませんが、その心の針を、しっかりと菩薩の世界に定めることを第二則でやります。
そして、「信仰とは主と一体となること」ですが、そのためには、もう一段の心の作業が要ります。それが第3則です。
それは、洗濯でいうと「染み抜き」にあたることです。染みが残っている部分というのは、主と一体となるときに、例えば移植手術でいう「拒否反応」みたいなものを起こし、それが妨げとなります。
一般的には、染みの三大要因は、「家庭環境」と「教育」と「職業訓練」だと教えて頂いています。
「両親の考え方が先生とぴったり同じだ」という方は、いないはずです。そのギャップのところに染みが存在します。
二つ目が教育。私達には少なからず偏向要因となっているはずです。
現代の二大阻害要因は、「マスコミ」と「教育」ですが、既にマスコミにはパンチを食らわせていますから、来年は『教育の法』で、左翼的考え方に光を当て改革していきます。
三つ目は職業特性です。
これら三大要素の中で、特に象徴的なのは両親の価値観です。ここで無意識に刷り込まれてくる「染み」から自由になることが、本当の意味で信仰が立ってくることと大きな関連があります。
ここで最後の染み抜きをやって、
「エル・カンターレの御前での誓いを思い出す」
という第四則に入ります。
私も、何度もシミュレーションしてみたのですが、本当に誓ったものを思い出すには、まだもう一段、二段、真実に近いものを思い出すには足りないと思いましたので、更に第4則の冒頭で、準備と工夫を加えました。
皆様の人生計画、或いは「誓い」は、誰が預かっているのでしょうか。
守護霊・指導霊ですね。その存在に、何十年間導かれてきたわけです。
それを正確に受け取る必要があります。比喩的に言えば、
「私はどう誓い、どう書いて、何を託してきたのでしょうか?」
ということです。
そのためには、様々なこの世的制約条件から自由になっていくことが必要ですが、そのためにどうしなければならないかを、御法話『心の中の宇宙』で仰っています。
潜在意識の水底を観る
一つ目は、自我意識。例えば湖そのものが仏であるならば、私達も本来、その湖に溶け込んで仏と一体となった、湖面の凪いだ(ないだ)湖そのものです。
そして自我意識とは、その湖面に波が立って、その波頭の一つひとつが自分だと思っていることです。本当は、あなたは湖そのものであったのに、その波頭の一個一個の大きさを競ったり、互いに嫉妬したりしている。それがこの世の現実です。
「自分が湖そのものなのだ」と気がつくためには、さざなみを鎮める必要があります。自我意識の統御、仏教的な「無我の修行」がこれにあたり、湖面が鏡のように平らかになります。
しかし、これだけでは、「誓い」の中身を受け取るには、十分ではありません。
湖面が平らになっても、本当の潜在意識、本来の自己が思っていることは、その湖底に書いてあるのですが、それを観るにためは、湖の水の透明度が高くなければなりません。濁っていたら、水底まで見えないのです。
この「にごり水」に当たるものは何か、これが「雑念」です。
濁る原因は、必ずしも「悪想念」だけではありません。「悪想念」だけならば、憑依現象が生じますので、先ず悪霊を取る反省行が必要となり、話としては、もう一つ前の段階となります。
ここで言う「雑念」とは、自分の心の中に飛び交っている、“腹減った”とか、“今晩のおかず何かな~”とか、“旦那は何時に帰ってくるかな~”という、無意識に心の中でつぶやいていること、このノイズのことを言います。
心の世界ではノイズとなって飛び交っているので、守護霊との交信が妨げられてくるのです。
宗務本部の人を霊査すると、守護霊と同通することがありますでしょ。例えば、先生にお茶出しをするときに、至近距離で“腹減った”とか思っていると、比喩的に言うと、「腹減った~」と大声で叫んでいるようなものです。
ですから、「雑念を出さない」という訓練が要ります。そうするとノイズが減ってきて、湖水の透明度が増し、潜在意識と同通しやすく(水底が見えやすく)なります。
つまり、「心の針が上を向いていればいい」というだけでもないのです。
湖水を透明にするためには、「無念無想」が必要です。余計なことを思わないということですね。これは、訓練によって、ある程度できるようになっていきます。
守護指導霊の声を正確に受け止めるには、ノイズを減らしてきれいな湖水にすること、つまり、湖底に何が書いてあるか文字が観えてくるためには、湖面の波を鎮めるだけではなく、湖水の透明度を高めて雑音をなくしていく、仏教的には『無念無想』の修行が必要なのです。
本当は、精舎修行の精度を高めるには、『無我』と『無念無想』の両方の修行が必要になります。「守護指導霊の声を聞きましょう」というのを、本当にきっちりやろうとしたら、この両方が前提になります。
そして、これをやるご法話研修があります。
『精神統一の方法』という修法がありますが、この中で『無我観』と『無念無想禅』が実修されています。
このように、第1則~第3則で魂の自由を回復したのちに、長時間ではありませんが『無我観』と『無念無想禅』を実修して、万全に準備を整えた上で、
「自分は生前、主エル・カンターレの御前で何を誓ってきたのか」、
それを心を解放して、恐れや迷いを取り除いた状態で、かつノイズにじゃまされない状態で、ストンと受け取ったときに、多分、皆様が自分の表面意識で考えていたことと違うものを観るはずです。
もっと、もっと、ずっと大きいものを観るはずです。
感化力は"勇気"から生まれる
その「ずっと大きなもの」を観たときに、人は本来の使命に目覚めざるを得ません。
そして、それを実現するための第一歩、第二歩を踏み出すことは、とても勇気が要ることですが、その行動を踏み始めた時に、
皆様は、今まで自分が活動の制約とか限界だと思っていたこと、そして何だかんだと言ってきたことが、さーっと壁が崩れ落ちるように無くなっていくのを見ることしょう。それをするのが、最後の第五則です。
第四則で本来の自己と出会います。そして、「その本来の自己が主との約束を果たす」というのは、いわば「師弟の道」にあたります。
それを実現するためには、誓ってきたことを心の中で思っているだけでは意味がありませんので、行動にあらわす必要があります。それには「勇気」が要ります。
つまり、自分のこの世的な頭で考えて、「この程度のことだな」と思っていることを実行するには、それほど勇気は要りませんが、「この世の自分が縮み上がるくらいのこと」をやろうとすると、勇気が要ります。
「本来の中道とは、そのあたりにある」
と、主からも教えられています。
そういうことをやろうとしたら、やっぱり『勇気』が要りますね。
そして、その『勇気』ある一歩を踏み出したときに、人間には『感化力』が出てくるんです。
『感化力』はどこから出てくるかというと、『勇気』を出した時に出てくるのです。『勇気』を振り絞ったときに、人はその姿を見て感動して、その方に『感化力』が生まれるのです。
大して勇気が要らないようなことを言ったり、やったりしても、人は別に感化されません。その一言を発し、
「"言った以上は実践する"と心に決めて、一歩踏み出したんだな、この人は」
と思える人から発されるオーラが、実は『感化力』なんです。
だから、『感化力』と『勇気』とは、一体です。
具体的に言うと、『伝道』や『植福』、もっと踏み込んで言えば、『勧進』ですね、つまり、『伝道』と『勧進』に置き換えていただければ、わかりやすいと思います。
「この人はちょっと無理かな」と思う相手に対しても、皆様に『感化力』が出てくると、違う結果が出てきます。伝道においても、勧進においても、それはそうです。
おそらく、心の中で思っておられる活動上の限界は、伝道においても、植福においても、同じところが原因なのだと思うのです。
限界は確かにあります。しかし、それは、
「今の『感化力』では、そこまでが限界なのだ」
ということをあらわしているのですね。
でも、その『感化力』に変化が出てくると、現れる結果が変わってくるのです。説得されなかった人が、説得されるようになってきます。
「この人は無理かな」と思っている人が、無理でなくなってくるという現象が起き始めるんです。
『感化力』をもたらすものは、『勇気』で、その『勇気』はどこから出てくるかというと、「自分は本当は、エル・カンターレの御前でここまで誓ってきたんだ」
ということを、自分の中で受け入れることです。
それが腑に落ちると、『勇気』が出てきて、それが『感化力』となって現れてきます。これは断言できます。
その方の「伝道する力」や「勧進する力」の次元が、変わってくるのです。
なぜ変わるかというと、宗教の世界では、自力だけじゃないですよね。本格的に他力が及んでくるんです。
単純に2倍じゃなくて、自分の『感化力』が2倍になると、それにふさわしい光が及んでくるので、実際相手が受ける光は2倍にとどまらず、3倍4倍になってくるという、これが宗教の素晴らしいところで、この世的な事業と決定的に違うところです。
ここまで踏み込んだ『感化力』は、倍ではないのです。そこにオーバーラップしてくるものがあるので、支部や様々ところでの活動に影響をもたらしてゆきます。
いろいろな限定が外れて、今までなら及ばなかった説得ができ、相手に感動を与え、その相手の方にも本来の自己を思い出して頂けるように、その方のハート、魂にまで届くようになってくると、
前提がすべて変わってきて、「目標」だったものが、「通過点」や「プロセス」だったことが、本心でわかります。
これが、実は冒頭申し上げた、
「目的と手段の関係がわかってくる」
ということの意味なのです。
「結果としての数字が、あとからついてくる」ということですね。
「こういう活動を目指したい」というのが、今回の活動推進局の名称替えの主旨の一つであり、同時にこの研修の目指していることでもあります。
もし、自我に囚われた心境で思い浮かべられるのものが、主と約束してきたことの内容だとしたら、残念だけれども、幸福の科学は世界宗教になれません。
しかし、世界宗教になることは、運命、天命です。
だから、皆様方の約束してきたものは、もう一段も二段も、大きいもののはずなのです。
今日の話は、非常に重要な内容ですので、道内の支部ルートでも、レジュメで流す予定です。ぜひ全国の法友の方にもお伝えください。
本日は本当にありがとうございました。(拍手)
どうか、繰り返し読んでください。
この内容を学ぶこむだけで、二つ以上の研修でいただく学びの深さがあると思います。
(特にひっかかったキーワードはノートに書いてそのテーマで深く思慧されることをオススメ!)
実はその意味で、この講話自体が一つの「禊ぎ」になってるんですよね。
さすが、年末にふさわしいご講話です。小林館長、おそるべし!!!!!
__________
(前編よりつづき)
入念な準備をした上で
多くの霊人も仰っておられますけれども、主エル・カンターレ本仏はひたすら大きいので、例えばその大きさは、
「釈迦とキリストの悟りが手のひらに乗って見えた」
と『フランクリー・スピーキング』にありました。この前の「韓信の霊言」によれば、
「仏陀の時と違って、主エル・カンターレを支えるには、脇士としてみたら、普賢菩薩みたいな方が100人位いないと担ぎ上げられません」
とありました。
それだけ巨大な方を信仰するということは、何を意味しているかというと、
「その百倍巨大な主の願いを実現することに命を賭けます」
ということを、表面上の言葉ではなく、他人向けのプレゼンテーションとしてではなく、それを本心から「誓い」、「帰依する」ということに他ならないのです。
つまり、「私達の目標が、本当は100倍あったのだ」ということを受け止めて、制約された"自我意識"がささやく、
「出来るわけないよ」
という言葉に打ち克っていくことが、必要なのです。
そのための入念な準備が、まさに第一則から第三則にあたるわけですが、北海道正心館版は、さらに工夫を凝らして、第4則の入り方に万全を期しました。
三次元の制約というのは大きいですので、その中でこれをしっかりと掴んでいくために、第一則では、「肉体の殻を脱ぎ捨てる」ことを、まず瞑想でやります。
この世的な経歴、性別、両親、家庭環境など、いわゆる「言い訳」の材料から自由になることです。
そして、肉体意識から自由になった心を、「一念三千」ではありませんが、その心の針を、しっかりと菩薩の世界に定めることを第二則でやります。
そして、「信仰とは主と一体となること」ですが、そのためには、もう一段の心の作業が要ります。それが第3則です。
それは、洗濯でいうと「染み抜き」にあたることです。染みが残っている部分というのは、主と一体となるときに、例えば移植手術でいう「拒否反応」みたいなものを起こし、それが妨げとなります。
一般的には、染みの三大要因は、「家庭環境」と「教育」と「職業訓練」だと教えて頂いています。
「両親の考え方が先生とぴったり同じだ」という方は、いないはずです。そのギャップのところに染みが存在します。
二つ目が教育。私達には少なからず偏向要因となっているはずです。
現代の二大阻害要因は、「マスコミ」と「教育」ですが、既にマスコミにはパンチを食らわせていますから、来年は『教育の法』で、左翼的考え方に光を当て改革していきます。
三つ目は職業特性です。
これら三大要素の中で、特に象徴的なのは両親の価値観です。ここで無意識に刷り込まれてくる「染み」から自由になることが、本当の意味で信仰が立ってくることと大きな関連があります。
ここで最後の染み抜きをやって、
「エル・カンターレの御前での誓いを思い出す」
という第四則に入ります。
私も、何度もシミュレーションしてみたのですが、本当に誓ったものを思い出すには、まだもう一段、二段、真実に近いものを思い出すには足りないと思いましたので、更に第4則の冒頭で、準備と工夫を加えました。
皆様の人生計画、或いは「誓い」は、誰が預かっているのでしょうか。
守護霊・指導霊ですね。その存在に、何十年間導かれてきたわけです。
それを正確に受け取る必要があります。比喩的に言えば、
「私はどう誓い、どう書いて、何を託してきたのでしょうか?」
ということです。
そのためには、様々なこの世的制約条件から自由になっていくことが必要ですが、そのためにどうしなければならないかを、御法話『心の中の宇宙』で仰っています。
潜在意識の水底を観る
一つ目は、自我意識。例えば湖そのものが仏であるならば、私達も本来、その湖に溶け込んで仏と一体となった、湖面の凪いだ(ないだ)湖そのものです。
そして自我意識とは、その湖面に波が立って、その波頭の一つひとつが自分だと思っていることです。本当は、あなたは湖そのものであったのに、その波頭の一個一個の大きさを競ったり、互いに嫉妬したりしている。それがこの世の現実です。
「自分が湖そのものなのだ」と気がつくためには、さざなみを鎮める必要があります。自我意識の統御、仏教的な「無我の修行」がこれにあたり、湖面が鏡のように平らかになります。
しかし、これだけでは、「誓い」の中身を受け取るには、十分ではありません。
湖面が平らになっても、本当の潜在意識、本来の自己が思っていることは、その湖底に書いてあるのですが、それを観るにためは、湖の水の透明度が高くなければなりません。濁っていたら、水底まで見えないのです。
この「にごり水」に当たるものは何か、これが「雑念」です。
濁る原因は、必ずしも「悪想念」だけではありません。「悪想念」だけならば、憑依現象が生じますので、先ず悪霊を取る反省行が必要となり、話としては、もう一つ前の段階となります。
ここで言う「雑念」とは、自分の心の中に飛び交っている、“腹減った”とか、“今晩のおかず何かな~”とか、“旦那は何時に帰ってくるかな~”という、無意識に心の中でつぶやいていること、このノイズのことを言います。
心の世界ではノイズとなって飛び交っているので、守護霊との交信が妨げられてくるのです。
宗務本部の人を霊査すると、守護霊と同通することがありますでしょ。例えば、先生にお茶出しをするときに、至近距離で“腹減った”とか思っていると、比喩的に言うと、「腹減った~」と大声で叫んでいるようなものです。
ですから、「雑念を出さない」という訓練が要ります。そうするとノイズが減ってきて、湖水の透明度が増し、潜在意識と同通しやすく(水底が見えやすく)なります。
つまり、「心の針が上を向いていればいい」というだけでもないのです。
湖水を透明にするためには、「無念無想」が必要です。余計なことを思わないということですね。これは、訓練によって、ある程度できるようになっていきます。
守護指導霊の声を正確に受け止めるには、ノイズを減らしてきれいな湖水にすること、つまり、湖底に何が書いてあるか文字が観えてくるためには、湖面の波を鎮めるだけではなく、湖水の透明度を高めて雑音をなくしていく、仏教的には『無念無想』の修行が必要なのです。
本当は、精舎修行の精度を高めるには、『無我』と『無念無想』の両方の修行が必要になります。「守護指導霊の声を聞きましょう」というのを、本当にきっちりやろうとしたら、この両方が前提になります。
そして、これをやるご法話研修があります。
『精神統一の方法』という修法がありますが、この中で『無我観』と『無念無想禅』が実修されています。
このように、第1則~第3則で魂の自由を回復したのちに、長時間ではありませんが『無我観』と『無念無想禅』を実修して、万全に準備を整えた上で、
「自分は生前、主エル・カンターレの御前で何を誓ってきたのか」、
それを心を解放して、恐れや迷いを取り除いた状態で、かつノイズにじゃまされない状態で、ストンと受け取ったときに、多分、皆様が自分の表面意識で考えていたことと違うものを観るはずです。
もっと、もっと、ずっと大きいものを観るはずです。
感化力は"勇気"から生まれる
その「ずっと大きなもの」を観たときに、人は本来の使命に目覚めざるを得ません。
そして、それを実現するための第一歩、第二歩を踏み出すことは、とても勇気が要ることですが、その行動を踏み始めた時に、
皆様は、今まで自分が活動の制約とか限界だと思っていたこと、そして何だかんだと言ってきたことが、さーっと壁が崩れ落ちるように無くなっていくのを見ることしょう。それをするのが、最後の第五則です。
第四則で本来の自己と出会います。そして、「その本来の自己が主との約束を果たす」というのは、いわば「師弟の道」にあたります。
それを実現するためには、誓ってきたことを心の中で思っているだけでは意味がありませんので、行動にあらわす必要があります。それには「勇気」が要ります。
つまり、自分のこの世的な頭で考えて、「この程度のことだな」と思っていることを実行するには、それほど勇気は要りませんが、「この世の自分が縮み上がるくらいのこと」をやろうとすると、勇気が要ります。
「本来の中道とは、そのあたりにある」
と、主からも教えられています。
そういうことをやろうとしたら、やっぱり『勇気』が要りますね。
そして、その『勇気』ある一歩を踏み出したときに、人間には『感化力』が出てくるんです。
『感化力』はどこから出てくるかというと、『勇気』を出した時に出てくるのです。『勇気』を振り絞ったときに、人はその姿を見て感動して、その方に『感化力』が生まれるのです。
大して勇気が要らないようなことを言ったり、やったりしても、人は別に感化されません。その一言を発し、
「"言った以上は実践する"と心に決めて、一歩踏み出したんだな、この人は」
と思える人から発されるオーラが、実は『感化力』なんです。
だから、『感化力』と『勇気』とは、一体です。
具体的に言うと、『伝道』や『植福』、もっと踏み込んで言えば、『勧進』ですね、つまり、『伝道』と『勧進』に置き換えていただければ、わかりやすいと思います。
「この人はちょっと無理かな」と思う相手に対しても、皆様に『感化力』が出てくると、違う結果が出てきます。伝道においても、勧進においても、それはそうです。
おそらく、心の中で思っておられる活動上の限界は、伝道においても、植福においても、同じところが原因なのだと思うのです。
限界は確かにあります。しかし、それは、
「今の『感化力』では、そこまでが限界なのだ」
ということをあらわしているのですね。
でも、その『感化力』に変化が出てくると、現れる結果が変わってくるのです。説得されなかった人が、説得されるようになってきます。
「この人は無理かな」と思っている人が、無理でなくなってくるという現象が起き始めるんです。
『感化力』をもたらすものは、『勇気』で、その『勇気』はどこから出てくるかというと、「自分は本当は、エル・カンターレの御前でここまで誓ってきたんだ」
ということを、自分の中で受け入れることです。
それが腑に落ちると、『勇気』が出てきて、それが『感化力』となって現れてきます。これは断言できます。
その方の「伝道する力」や「勧進する力」の次元が、変わってくるのです。
なぜ変わるかというと、宗教の世界では、自力だけじゃないですよね。本格的に他力が及んでくるんです。
単純に2倍じゃなくて、自分の『感化力』が2倍になると、それにふさわしい光が及んでくるので、実際相手が受ける光は2倍にとどまらず、3倍4倍になってくるという、これが宗教の素晴らしいところで、この世的な事業と決定的に違うところです。
ここまで踏み込んだ『感化力』は、倍ではないのです。そこにオーバーラップしてくるものがあるので、支部や様々ところでの活動に影響をもたらしてゆきます。
いろいろな限定が外れて、今までなら及ばなかった説得ができ、相手に感動を与え、その相手の方にも本来の自己を思い出して頂けるように、その方のハート、魂にまで届くようになってくると、
前提がすべて変わってきて、「目標」だったものが、「通過点」や「プロセス」だったことが、本心でわかります。
これが、実は冒頭申し上げた、
「目的と手段の関係がわかってくる」
ということの意味なのです。
「結果としての数字が、あとからついてくる」ということですね。
「こういう活動を目指したい」というのが、今回の活動推進局の名称替えの主旨の一つであり、同時にこの研修の目指していることでもあります。
もし、自我に囚われた心境で思い浮かべられるのものが、主と約束してきたことの内容だとしたら、残念だけれども、幸福の科学は世界宗教になれません。
しかし、世界宗教になることは、運命、天命です。
だから、皆様方の約束してきたものは、もう一段も二段も、大きいもののはずなのです。
今日の話は、非常に重要な内容ですので、道内の支部ルートでも、レジュメで流す予定です。ぜひ全国の法友の方にもお伝えください。
本日は本当にありがとうございました。(拍手)
エル・カンターレとの約束を思い出す(前編)
2010年12月31日
このお話は、非常に重要です。
このお話自体が二つ以上の研修を受けるのに等しい内容です。
どうか繰り返し読んでみてください。
3回目、4回目でどんどんしみこんできますので。
小林館長、かなり本気モードです。
__________
七の日感謝祭ご講話 北海道正心館小林早賢館長
「エル・カンターレとの約束を思い出す」
皆さまこんにちは。今日はようこそ、北海道正心館『七の日感謝祭』にお越しいただき、ありがとうございます。
今日は、先日の支部長情報交流会に関連して、来年のことを考えて一番中核になるテーマを取り上げ、年明けから始まる『信仰を深めるためには』公案研修を探究していく上で重要なことを~更に北海道正心館ではもう一段、練り込みをしてありますけれども、それが来年1月8日から開示になるのですが、(既にかなりの支部からオーダー研修の予約を頂いておりますが)~今後一番重要なテーマでありますので、年末の締めくくりとして、そのお話をさせていただきます。
情報交流会での発表がいろいろありましたが、特筆すべき点は、活動推進局が『エル・カンターレ信仰伝道局』という名称に衣替えしたことです。一番大きな変化だと思います。
これは、単なる名称変更にとどまらず、色々なことを、今後、変えていくことになると思います。名前というのは、それほど大きな理念を含んだものです。
そういう視点で見てみると、いろんな変化を作っていくだろう、むしろ作り出していくべきだろうと思っています。
その背景について、もう一段、説明しておきたいと思います。
これは、先生のお言葉として何度か耳にされた方もいらっしゃると思いますが、自然に流しておくと、どうしても地上においては、21世紀のこういう時代に、つまりイエスのような時代ではなく、現代の高度な経済社会で、こういう宗教活動をしていると、結果的には、「活動形態がやや税務署に近くなる」と言われています。
ややもすると、「行動パターンが税務署型になる」というのは、皆さんもお感じになっていると思います。
別の言い方をすると、「統計局」型の行動~数字の報告を求める~になってくる。
(削っても削っても、数字の報告がまた増える。「報告業務のリストラかけても、また元に戻って、結構な報告量になる」というのを20年間繰り返していますね。)
また、ややもすると、ご教示を伝える「連絡局」型の行動になる。
機能としては、税務局兼統計局兼連絡局という、こういう感じなると言われているわけです。
もちろん、この世的には、そういう活動が付随するのは、あることなのですが、ただ、それらは手段、或いは結果であって、「目的と結果の関係」、或いは「目的と手段の関係」をよく考えないといけないのですね。
私達の「目的」は、エル・カンターレ信仰を広めることです。その結果、色々な数字が出てきて、「みんなで喜びを分かち合う」ということになります。
ただ、ここが微妙なのですが、「結果に囚われない」ということを言っている訳でもないし、さりとて、「結果が目的になる」と宗教ビジネスのように見えることもあるので、これの「中道」をよく捉えないといけません。
経済や生活全般が、現代ほど複雑でなかった仏陀、イエスの時代に比べると、現代は、このあたりが難しいと思います。
「目的と結果の関係」をさらに説明すると、先生がこれを人体に喩えて(たとえて)仰ってくださったことがあるのですが、「目的」というのは「頭脳」にあたります。また成果測定をする箇所は、「下半身」に相当します。
組織を人間の人体に置き換えると、「頭脳」というのは指令を発信するところ、つまり「目的」にあたります。その目的がつつがなく流れるために、下半身が三次元でダチョウのごとく駆けて「結果」を出す、そういう意味で、先ほど述べたような活動(報告、連絡等)が「下半身」に相当するわけです。
(下半身しかないダチョウは、変ですね(笑)。)
こういう全体像をよく腑に落としておかないと、ともすると目的と手段の関係が逆転しかねない部分は、過去20年間ありまして、かくの如く先生のご指摘もありました。
本当の意味で「目的」をしっかり打ち立ててやっていく。そのプロセスで、統計的側面も出てくるわけですが、
「主従を間違えてはいけない」ということです。
「その目的である「信仰」が、どれくらい大きなものなのか」
それを掴んでいくために、『信仰を深めるために』公案研修の意義について、これからお話したいと思います。
『信仰を深めるために』公案研修の意義
『あなた方は、主エル・カンターレの本当の姿の100分の1も掴んでいない』と、霊人の言葉にもありました。
「なぜ今の私達が、100分の1にとどまっているのか」ということと、本研修は関連があります。
この研修は、「仏陀特別霊指導」で、全5則です。第4則がクライマックスです。
北海道正心館版では、もう一段工夫を加えて、内部の実験研修を大晦日の日にやります。更に、今回は支部長向けのプレ研修を1月6日に行います(講師:館長)。
そうして、本格的に1月8日から開示いたします。
公案の中身は、もちろん申し上げられませんが、その主旨、意味合いは何かといいますと、
「皆様方が生まれてくる前に主の御前で誓った中身」、これは結構重いと思うのですけれど、「私達は生まれる前に、その主の御前で何を誓って出てきたのか。それを思い出せ」、
これが第4則です。
これで十分、この研修の念い、重要性、意義がおわかりになると思います。
私達は、本仏の前で誓って出てきたんですね。
これ、今までに弟子が、ニュアンスとして語ってきたことはあったと思いますが、現実に、ここまでストレートな「仏言」として出てきたのは、初めてだと思います。
そもそも、本仏の存在を知っていた。その本仏の前で誓いを立てた。そして、その誓いが存在したがゆえに、私達は、この時代に生まれることが許された。
そして、その誓いを思い出すことは、とても重要なことではありますが、
「これは簡単なことじゃないぞ。本当に深いところまで、自分が誓ったことを思い出せる、そこまで霊的になれるというのは…これは生半可なことじゃないぞ」
と、3年5年10年と修行された方であれば、おわかりなのではないでしょうか。
今世のこの世の自分から、自由になる
日々感じておられると思いますが、どうしても3次元で生きていますと、この世的な自分に束縛されて、己を小さく小さく考えてしまいます。
その小さな自分と決別したくて、脱皮したくて、精舎修行に来られます。
一泊研修などして、その晩あたりから、俗世の塵垢(ちりあか)が取れてきて、本来の自己に向き合って、
「本当の自分はこんな小さくないのだ」
と悟り、そして、
「信仰をとおして主と一体になって、もっと大きな自分になれるんだ!」
と掴むのだけれど、下山して3日から1週間過ぎると、その思いが切れてくる。で、また精舎修行に行く。
単純な繰り返しをしているように見えますが、実は前進しています。何度も何度も繰り返していくことで、確実に前進しているのですが、
皆様の成長に応じて、当会自体も大きくなり、各自にかかってくる負荷も大きくなっているので、格闘している精神状態は、同じように見えますが、第三者からみると、間違いなく成長しています。
日常生活の中で、色々な出来事があると、自分を小さく捉えてしまうものです。だから、
「こんな小さな自分が約束できることなんて、この程度じゃないか」
と、無意識のうちに小さく考えてしまうんです。
この世の自我に囚われた(とらわれた)状態で、約束してきたことを思い出そうとしても、
そこで思いついた「約束」は、本来の自己から見れば、とてもそれを「誓って」、生まれてきたわけではない、というものなのです。
もしそれで、エル・カンターレとの誓いを思い出せるなら、この研修が存在する意義はありません。
日常の生活の中に囚われている意識では思い出せない「誓い」とは、一体、何だったのか。
「そこまで深く立ち入って、エル・カンターレとの誓いを掴む」
これが、この研修の目的です。
これは半端なことではありません。妨げているのは、「自我意識」です。具体的に言うと、今世のこの名前で生きているという、その枠の中で生きているという意識が、「自由な自分」を妨げているのですから、ここに制約があります。
自分を捕らえているもの:地域、両親、職業、教育…
私達は何百、何千、何万転生という豊富な経験を持っています。表面意識は、それらに直接アクセスできませんが、潜在意識には、智慧と経験が蓄積されていて、
「それが表面意識ににじみ出てくる」
という意味では、アクセス可能です。
例えば、ある地域(北海道・日本)に生まれたという事実があると、その地域特性とか言語、文化に囚われた制約があります。
例えば地球の裏側のブラジルの方の発想。先般のブラジルご巡錫でも皆さんご覧になったと思いますが、初めて会った人をスタンディング・オベーションで迎えられました。
さっそく直後の横浜アリーナ(12/4)で、日本の人が真似していましたね。先般の熊本でも真似していました。この20年間、日本では誰も思いつかなかった発想です。
この生まれ育った環境に制約された生き方をしているんです。
ブラジルは、カルチャー遺伝子的には、元々の南米大陸に加えて、ポルトガル、南ヨーロッパ(一部アフリカ)等ですから、どこかの転生で、皆さんも接触はあったはずです。要するに考え方の遺伝子としては、どこかで触れているのですが、今世、表面意識の環境制約に囚われていると(ex.日本人は自分の方か
ら積極的に好意を表現しない)、彼らのような発想が出てこない。
自分を小さく見ているという点で、さらに影響が大きいのは、
「この両親の下で生まれた」
という制約です。これは、白紙に戻して観ることができます。ここは公案(第3則)にも出てきます。
この両親の下で、この両親の人生観によって、少なくとも成人するまで育てられた。
「信仰とは、親の価値観からの独立でもある」
と、2007年大阪中央支部での『純粋な信仰』の質疑応答にありましたが、親の価値観ではなく、主の価値観を選び取るということが、「信仰が立つ」という上で、重要な意味があるのがわかります。
これは皆様も、なかなか、出来ているようで出来ていないのではないかと、無意識に背負っているように見えます。そこから完全に解脱し、自由になっているか。そういう意味で信仰が立っているかどうか。
また、たまたま選んだ、(もしかしたら流れで選んだのかもしれない)「職業」からの制約もあります。
職業は、魂の傾向性をつくりますから、職業特性から出てくる人格というのもあります。そこから自由になった自分は、また違う個性かもしれません。
今世、私は「公務員」でしたが、もしかしたら「貿易商人」だったかもしれません。
実は、全く違う遺伝子を潜在意識は持っているのだけれども、それが遮断されていて、色々な可能性があることに気がつかない。
しかし、そこで信仰が立つことによって、今世の職業経験から自由になると、自分にはもっと可能性があることが見えてきます。
また、さらに長い視点で見てみると、今世における「経歴」も、たまたまの偶然の要素があったのかもしれません。
私も今世、ご存じの大学を出て、ご存じの組織に就職し、その後出家したわけですが、
(レジメでは詳述は避けますけれども)、どこかでボタンが一つかけ違っていたら、まったく違う人生のプロセスを経て、例えば夜間大学に行き、まったく違う職業に就いていたかも知れません。
その場合、今52歳にして、この時点まで全く違うプロセスを辿ったとして、この2010年12月27日の時点で、北海道正心館のこの演台に立っているだろうかと考えてみたとき、
直感としては、「やはり立っている」という気がします。
だから、「経歴」というのは相対的なものであって、主体である「意志」と「情熱」が、環境をつくり出していくのだと思うのです。
ということで、「経歴」からの制約もあります。また「家族」からの制約もあります。「伴侶」、「子供」、「親」、「学歴」、「外見」、「体力」etc.…。
誰もに今世の制約条件があり、その制約の中で発想し、行動しています。
ただ、それらは「思い」の中で乗り越えることができ、違う自分を引っ張り出すことは可能です。
こういう制約だらけの中で生きている自分が、自然のままで、
「仏の御前で、生前、約束してきたことは何か」
といういことを考えたら、「小さな目標」や「小さな目的」を考えてしまうはずなんです。
この限界を、「信仰」の力によって突破しなければならないのです。
(後編につづく)
このお話自体が二つ以上の研修を受けるのに等しい内容です。
どうか繰り返し読んでみてください。
3回目、4回目でどんどんしみこんできますので。
小林館長、かなり本気モードです。
__________
七の日感謝祭ご講話 北海道正心館小林早賢館長
「エル・カンターレとの約束を思い出す」
皆さまこんにちは。今日はようこそ、北海道正心館『七の日感謝祭』にお越しいただき、ありがとうございます。
今日は、先日の支部長情報交流会に関連して、来年のことを考えて一番中核になるテーマを取り上げ、年明けから始まる『信仰を深めるためには』公案研修を探究していく上で重要なことを~更に北海道正心館ではもう一段、練り込みをしてありますけれども、それが来年1月8日から開示になるのですが、(既にかなりの支部からオーダー研修の予約を頂いておりますが)~今後一番重要なテーマでありますので、年末の締めくくりとして、そのお話をさせていただきます。
情報交流会での発表がいろいろありましたが、特筆すべき点は、活動推進局が『エル・カンターレ信仰伝道局』という名称に衣替えしたことです。一番大きな変化だと思います。
これは、単なる名称変更にとどまらず、色々なことを、今後、変えていくことになると思います。名前というのは、それほど大きな理念を含んだものです。
そういう視点で見てみると、いろんな変化を作っていくだろう、むしろ作り出していくべきだろうと思っています。
その背景について、もう一段、説明しておきたいと思います。
これは、先生のお言葉として何度か耳にされた方もいらっしゃると思いますが、自然に流しておくと、どうしても地上においては、21世紀のこういう時代に、つまりイエスのような時代ではなく、現代の高度な経済社会で、こういう宗教活動をしていると、結果的には、「活動形態がやや税務署に近くなる」と言われています。
ややもすると、「行動パターンが税務署型になる」というのは、皆さんもお感じになっていると思います。
別の言い方をすると、「統計局」型の行動~数字の報告を求める~になってくる。
(削っても削っても、数字の報告がまた増える。「報告業務のリストラかけても、また元に戻って、結構な報告量になる」というのを20年間繰り返していますね。)
また、ややもすると、ご教示を伝える「連絡局」型の行動になる。
機能としては、税務局兼統計局兼連絡局という、こういう感じなると言われているわけです。
もちろん、この世的には、そういう活動が付随するのは、あることなのですが、ただ、それらは手段、或いは結果であって、「目的と結果の関係」、或いは「目的と手段の関係」をよく考えないといけないのですね。
私達の「目的」は、エル・カンターレ信仰を広めることです。その結果、色々な数字が出てきて、「みんなで喜びを分かち合う」ということになります。
ただ、ここが微妙なのですが、「結果に囚われない」ということを言っている訳でもないし、さりとて、「結果が目的になる」と宗教ビジネスのように見えることもあるので、これの「中道」をよく捉えないといけません。
経済や生活全般が、現代ほど複雑でなかった仏陀、イエスの時代に比べると、現代は、このあたりが難しいと思います。
「目的と結果の関係」をさらに説明すると、先生がこれを人体に喩えて(たとえて)仰ってくださったことがあるのですが、「目的」というのは「頭脳」にあたります。また成果測定をする箇所は、「下半身」に相当します。
組織を人間の人体に置き換えると、「頭脳」というのは指令を発信するところ、つまり「目的」にあたります。その目的がつつがなく流れるために、下半身が三次元でダチョウのごとく駆けて「結果」を出す、そういう意味で、先ほど述べたような活動(報告、連絡等)が「下半身」に相当するわけです。
(下半身しかないダチョウは、変ですね(笑)。)
こういう全体像をよく腑に落としておかないと、ともすると目的と手段の関係が逆転しかねない部分は、過去20年間ありまして、かくの如く先生のご指摘もありました。
本当の意味で「目的」をしっかり打ち立ててやっていく。そのプロセスで、統計的側面も出てくるわけですが、
「主従を間違えてはいけない」ということです。
「その目的である「信仰」が、どれくらい大きなものなのか」
それを掴んでいくために、『信仰を深めるために』公案研修の意義について、これからお話したいと思います。
『信仰を深めるために』公案研修の意義
『あなた方は、主エル・カンターレの本当の姿の100分の1も掴んでいない』と、霊人の言葉にもありました。
「なぜ今の私達が、100分の1にとどまっているのか」ということと、本研修は関連があります。
この研修は、「仏陀特別霊指導」で、全5則です。第4則がクライマックスです。
北海道正心館版では、もう一段工夫を加えて、内部の実験研修を大晦日の日にやります。更に、今回は支部長向けのプレ研修を1月6日に行います(講師:館長)。
そうして、本格的に1月8日から開示いたします。
公案の中身は、もちろん申し上げられませんが、その主旨、意味合いは何かといいますと、
「皆様方が生まれてくる前に主の御前で誓った中身」、これは結構重いと思うのですけれど、「私達は生まれる前に、その主の御前で何を誓って出てきたのか。それを思い出せ」、
これが第4則です。
これで十分、この研修の念い、重要性、意義がおわかりになると思います。
私達は、本仏の前で誓って出てきたんですね。
これ、今までに弟子が、ニュアンスとして語ってきたことはあったと思いますが、現実に、ここまでストレートな「仏言」として出てきたのは、初めてだと思います。
そもそも、本仏の存在を知っていた。その本仏の前で誓いを立てた。そして、その誓いが存在したがゆえに、私達は、この時代に生まれることが許された。
そして、その誓いを思い出すことは、とても重要なことではありますが、
「これは簡単なことじゃないぞ。本当に深いところまで、自分が誓ったことを思い出せる、そこまで霊的になれるというのは…これは生半可なことじゃないぞ」
と、3年5年10年と修行された方であれば、おわかりなのではないでしょうか。
今世のこの世の自分から、自由になる
日々感じておられると思いますが、どうしても3次元で生きていますと、この世的な自分に束縛されて、己を小さく小さく考えてしまいます。
その小さな自分と決別したくて、脱皮したくて、精舎修行に来られます。
一泊研修などして、その晩あたりから、俗世の塵垢(ちりあか)が取れてきて、本来の自己に向き合って、
「本当の自分はこんな小さくないのだ」
と悟り、そして、
「信仰をとおして主と一体になって、もっと大きな自分になれるんだ!」
と掴むのだけれど、下山して3日から1週間過ぎると、その思いが切れてくる。で、また精舎修行に行く。
単純な繰り返しをしているように見えますが、実は前進しています。何度も何度も繰り返していくことで、確実に前進しているのですが、
皆様の成長に応じて、当会自体も大きくなり、各自にかかってくる負荷も大きくなっているので、格闘している精神状態は、同じように見えますが、第三者からみると、間違いなく成長しています。
日常生活の中で、色々な出来事があると、自分を小さく捉えてしまうものです。だから、
「こんな小さな自分が約束できることなんて、この程度じゃないか」
と、無意識のうちに小さく考えてしまうんです。
この世の自我に囚われた(とらわれた)状態で、約束してきたことを思い出そうとしても、
そこで思いついた「約束」は、本来の自己から見れば、とてもそれを「誓って」、生まれてきたわけではない、というものなのです。
もしそれで、エル・カンターレとの誓いを思い出せるなら、この研修が存在する意義はありません。
日常の生活の中に囚われている意識では思い出せない「誓い」とは、一体、何だったのか。
「そこまで深く立ち入って、エル・カンターレとの誓いを掴む」
これが、この研修の目的です。
これは半端なことではありません。妨げているのは、「自我意識」です。具体的に言うと、今世のこの名前で生きているという、その枠の中で生きているという意識が、「自由な自分」を妨げているのですから、ここに制約があります。
自分を捕らえているもの:地域、両親、職業、教育…
私達は何百、何千、何万転生という豊富な経験を持っています。表面意識は、それらに直接アクセスできませんが、潜在意識には、智慧と経験が蓄積されていて、
「それが表面意識ににじみ出てくる」
という意味では、アクセス可能です。
例えば、ある地域(北海道・日本)に生まれたという事実があると、その地域特性とか言語、文化に囚われた制約があります。
例えば地球の裏側のブラジルの方の発想。先般のブラジルご巡錫でも皆さんご覧になったと思いますが、初めて会った人をスタンディング・オベーションで迎えられました。
さっそく直後の横浜アリーナ(12/4)で、日本の人が真似していましたね。先般の熊本でも真似していました。この20年間、日本では誰も思いつかなかった発想です。
この生まれ育った環境に制約された生き方をしているんです。
ブラジルは、カルチャー遺伝子的には、元々の南米大陸に加えて、ポルトガル、南ヨーロッパ(一部アフリカ)等ですから、どこかの転生で、皆さんも接触はあったはずです。要するに考え方の遺伝子としては、どこかで触れているのですが、今世、表面意識の環境制約に囚われていると(ex.日本人は自分の方か
ら積極的に好意を表現しない)、彼らのような発想が出てこない。
自分を小さく見ているという点で、さらに影響が大きいのは、
「この両親の下で生まれた」
という制約です。これは、白紙に戻して観ることができます。ここは公案(第3則)にも出てきます。
この両親の下で、この両親の人生観によって、少なくとも成人するまで育てられた。
「信仰とは、親の価値観からの独立でもある」
と、2007年大阪中央支部での『純粋な信仰』の質疑応答にありましたが、親の価値観ではなく、主の価値観を選び取るということが、「信仰が立つ」という上で、重要な意味があるのがわかります。
これは皆様も、なかなか、出来ているようで出来ていないのではないかと、無意識に背負っているように見えます。そこから完全に解脱し、自由になっているか。そういう意味で信仰が立っているかどうか。
また、たまたま選んだ、(もしかしたら流れで選んだのかもしれない)「職業」からの制約もあります。
職業は、魂の傾向性をつくりますから、職業特性から出てくる人格というのもあります。そこから自由になった自分は、また違う個性かもしれません。
今世、私は「公務員」でしたが、もしかしたら「貿易商人」だったかもしれません。
実は、全く違う遺伝子を潜在意識は持っているのだけれども、それが遮断されていて、色々な可能性があることに気がつかない。
しかし、そこで信仰が立つことによって、今世の職業経験から自由になると、自分にはもっと可能性があることが見えてきます。
また、さらに長い視点で見てみると、今世における「経歴」も、たまたまの偶然の要素があったのかもしれません。
私も今世、ご存じの大学を出て、ご存じの組織に就職し、その後出家したわけですが、
(レジメでは詳述は避けますけれども)、どこかでボタンが一つかけ違っていたら、まったく違う人生のプロセスを経て、例えば夜間大学に行き、まったく違う職業に就いていたかも知れません。
その場合、今52歳にして、この時点まで全く違うプロセスを辿ったとして、この2010年12月27日の時点で、北海道正心館のこの演台に立っているだろうかと考えてみたとき、
直感としては、「やはり立っている」という気がします。
だから、「経歴」というのは相対的なものであって、主体である「意志」と「情熱」が、環境をつくり出していくのだと思うのです。
ということで、「経歴」からの制約もあります。また「家族」からの制約もあります。「伴侶」、「子供」、「親」、「学歴」、「外見」、「体力」etc.…。
誰もに今世の制約条件があり、その制約の中で発想し、行動しています。
ただ、それらは「思い」の中で乗り越えることができ、違う自分を引っ張り出すことは可能です。
こういう制約だらけの中で生きている自分が、自然のままで、
「仏の御前で、生前、約束してきたことは何か」
といういことを考えたら、「小さな目標」や「小さな目的」を考えてしまうはずなんです。
この限界を、「信仰」の力によって突破しなければならないのです。
(後編につづく)