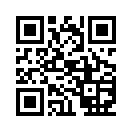奄美と沖縄(転載)
2011年06月21日
http://keybow49okinawan.web.fc2.com/ookubo/gensou.html
奄美と沖縄
沖縄の人の多くが、自らを「日本人」というよりも「沖縄人」と認識する理由の一つに、沖縄は日本とは違う歴史と文化を持つという「沖縄史観」があります。この「沖縄史観」を揺るがすかもしれない遺跡の調査が現在、鹿児島県の奄美大島の東方に浮かぶ喜界島で行われています。
2007年11月に琉球大学主催の「沖縄と奄美の経済交流フォーラム」が奄美大島で開かれ、琉大の後藤雅彦准教授から、喜界島で発掘が続く城久遺跡の報告がありました。この遺跡からは、古代末から中世の大規模な建物跡が見つかっています。出土品の中に中国や朝鮮製の磁器、九州の陶器があり、螺鈿(らでん)細工に珍重される夜光貝も大量に出土したことから、九州・大宰府の官人の駐在拠点と中国貿易を含む夜光貝の加工・物流センターであった可能性があるというのです。そうであれば、これまで薩摩侵攻(1609年)以前の歴史ではヤマトではなく沖縄の一地方と見られていた奄美諸島史が塗り替えられ、奄美はヤマトの最南端、しかもアジア交易の重要拠点だったことになるわけです。
これを、沖縄から見れば、沖縄はヤマトとは別の自律的な発展過程があり、沖縄本島を中心に王国が形成され、その影響が西方の先島諸島や東方の奄美諸島に広がっていったという沖縄中心史観が、覆ることになります。沖縄史観では辺境に位置する奄美大島の、さらに辺境の小島が実は先に発展して南西諸島の中心となり、沖縄に影響を与えた……。これまでの想定とは逆の文化の流れがあったのではないか、というのです。
この喜界島の考古学の発見は、さらに道州制の議論にも影響を与えそうです。沖縄は道州制の議論で「単独州は当然」と考えていますが、その際、歴史・文化的背景から、南西諸島というくくりで奄美も混ぜてしまおうという発想が文化人の中にあります。一方、奄美の方にも、「観光や振興策で潤う沖縄と合併できたらいい」(奄美のマスコミ関係者)という声があります。ところが、奄美の行政幹部は鹿児島系が主流で、沖縄合併論はタブーなのだそうです。きっと、奄美がヤマトに属することを証明する喜界島の発見は道州制の議論の中で鹿児島系の人たちに政治的に利用されるのでしょう。
世界一優しい声」として人気の歌手、中孝介や元ちとせ、「恵」「泉」「武」など奄美に一字の名字が多い(沖縄には一字はほとんどなく、三字が多い)のは、奄美出身とわかるように薩摩が採った政策だそうで、薩摩の一部には反薩摩感情もあります。一方、奄美は沖縄からも差別された歴史があるので、反沖縄感惰もあります。フォーラムに参加したある奄美出身の経済人は酒の席では「誰が沖縄の世話になんかなるか」とストレートに沖縄への反感を吐露していました。
佐野眞一氏の『沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史』には、奄美出身者が沖縄で受けたすさまじい差別の証言がいろいろと書かれてあり、読んでいてやりきれなくなります。那覇に住む奄美出身の知人も「基地問題で『日本人は沖縄を差別するなと言うのを聞くと『お前らがそんなこと言える立場か』と怒りがこみ上げる」と話していました。奄美諸島は沖縄より早く米国支配から解放され1953年に本土復帰しましたが、それにより沖縄で生活していた奄美出身者は「外国人」となり、選挙権がなくなったり、公職から追放されたりしました。奄美の人の沖縄に対する恨みは根深いものがあります。
沖縄では、文化人を中心に奄美との一体感が強張される一方で、「奄美なんてお荷物」と特に経済人は考えています。さらに、道州制で沖縄と九州が一緒になる構想について九州側からは「沖縄なんてお荷物を抱えたら、九州の財政が破たんする」(ある地方紙幹部)と拒否反応もあります。
地理的には「南西諸島」、歴史・文化圏としては「琉球弧」、思想的には奄美で暮らした作家島尾敏雄が唱えた「ヤポネシア」などの言葉でくくられる沖縄と奄美、沖縄には「琉球弧の先住民族会」という組織があります。「琉球弧の自立・独立」を掲げる「うるまネシア」という同人誌もあります。
国道58号線は那覇市から奄美、種子島、鹿児島市まで約600キロメートルの海上を挟んで結ぶロマンチックな道です。そんな兄弟のような沖縄と奄美でさえ、簡単には乗り越え難い溝があります。薩摩侵攻から400年、琉球処分から130年の節目の2OO9年。地域や民族の属性から離れて仲良くすることは本当に難しいことだと、つくづく思います。沖縄と本土の溝が簡単に埋まるわけがない、ましてパレスチナとユダヤが握手することの困難さは想像を絶するのだろう、などと思ってしまいます。
沖縄と宮古と八重山
沖縄は大きく、沖縄島(本島)宮古諸島、八重山諸島の3つに分かれ、それぞれ文化や言葉も違います。宮古と八重山を合わせて先島ということもあります。宮古や八重山の人は、本島に行くことを「沖縄に行く」と言います。これは、距離が離れているだけではなく、「沖縄本島とは同じではないという認識がある」(宮古島出身の経営者)と言います。
1609年に薩摩の支配を受けた琉球王朝は、人頭税を宮古と八重山に課します。貧富にかかわらず一律に上納が義務付けられるのですから、大変重い税です。宮古島には高さ143センチの「人頭税石」が今もあります。この身長になると人頭税がかけられたという説があるようです。この税制は琉球処分で沖縄県になった後の1903年にようやく廃止されます。2003年には東京・上野で「人頭税廃止100年コンサート」なるものが宮古出身の歌手らが参加して開かれていますから、怨みも重いようです。宮古に伝わる「アララガマ精神」(なにくそ、負けないぞ)は人頭税の歴史と結びついています。
与那国島西端の港町、久部良には「クブラバリ」という名所があります。断崖の上に3メートルほどの大きな岩の割れ目がある場所です。人頭税に苦しんだ島民は、人を減らすために、その割れ目を妊婦に飛ばしたというのです。体力のない母親はお腹の子供もろとも海の底に消えます。柵も何もないクブラバリの脇に立って穴をのぞくと、吸い込まれそうで足がすくみます。人頭税に苦しむ島民のために、首里の王朝に対し反乱を起こした石垣島の豪族オヤケアカハチは、今でも八重山の英雄です。
八重山の中心、石垣島の近くに浮かぶ竹富島の民謡「安里屋ユンタ」は、今ではすっかり沖縄を代表する唄になっています。「サァ 君は野中の茨の花か」とか「沖縄よいとこ 一度はおいで」と唄われる歌詞は後から付けた新バージョンで、本来は「サァ 安里屋ぬ クヤマによ」と唄われる労働歌です。メロディも少し違います。島の美人クヤマが首里から来た役人の求婚を断った、その気高さを讃える唄と書われています。沖縄民謡は普通、琉球音階(レとラを抜いた5音階)ですが、この最も有名な安里屋ユンタは、日本音階(ファとシを抜いた5音階)で作曲されています。ピアノだと黒鍵だけで弾けます。君が代や蛍の光と同じ音階です。八重山民謡には、琉球音階に対する反発からか、日本音階の曲も多いといいます。石垣島出身のBEGlNのポーカル、比嘉栄昇さんに話を聞いたときも「僕はレラ抜き(琉球音階)を信用していないんです。自然にレラ抜きになることはあっても、意識的には使いません」と言っていました。
宮古や八重山の人と話をすると、本土にもいろいろな地域がありそれぞれの文化があるように、沖縄も決して一枚岩ではない、むしろ「合衆国」だと感じます。ちなみに、安里屋ユンタのサビで繰り返される「マタハーリヌ チンダラ カヌシヤマョ」(なんと愛しい人だろ)が、戦争の時に日本軍の兵隊たちには「死んだら神さまよ」と聞こえたため本土にも広まった、という説があるようですが、本当でしょうか。
過去も含めてあえて大雑把に図式化すると、米国→日本→沖縄→奄美・宮古・八重山といった加害と被害の重構造があり、その中で沖縄は「日本は沖縄を差別している」と言い、日本は「沖縄だって奄美や宮古を差別しているじゃないか」と言い返す構図があります。あまり生産的な会話ではないことは確かでしょう
奄美と沖縄
沖縄の人の多くが、自らを「日本人」というよりも「沖縄人」と認識する理由の一つに、沖縄は日本とは違う歴史と文化を持つという「沖縄史観」があります。この「沖縄史観」を揺るがすかもしれない遺跡の調査が現在、鹿児島県の奄美大島の東方に浮かぶ喜界島で行われています。
2007年11月に琉球大学主催の「沖縄と奄美の経済交流フォーラム」が奄美大島で開かれ、琉大の後藤雅彦准教授から、喜界島で発掘が続く城久遺跡の報告がありました。この遺跡からは、古代末から中世の大規模な建物跡が見つかっています。出土品の中に中国や朝鮮製の磁器、九州の陶器があり、螺鈿(らでん)細工に珍重される夜光貝も大量に出土したことから、九州・大宰府の官人の駐在拠点と中国貿易を含む夜光貝の加工・物流センターであった可能性があるというのです。そうであれば、これまで薩摩侵攻(1609年)以前の歴史ではヤマトではなく沖縄の一地方と見られていた奄美諸島史が塗り替えられ、奄美はヤマトの最南端、しかもアジア交易の重要拠点だったことになるわけです。
これを、沖縄から見れば、沖縄はヤマトとは別の自律的な発展過程があり、沖縄本島を中心に王国が形成され、その影響が西方の先島諸島や東方の奄美諸島に広がっていったという沖縄中心史観が、覆ることになります。沖縄史観では辺境に位置する奄美大島の、さらに辺境の小島が実は先に発展して南西諸島の中心となり、沖縄に影響を与えた……。これまでの想定とは逆の文化の流れがあったのではないか、というのです。
この喜界島の考古学の発見は、さらに道州制の議論にも影響を与えそうです。沖縄は道州制の議論で「単独州は当然」と考えていますが、その際、歴史・文化的背景から、南西諸島というくくりで奄美も混ぜてしまおうという発想が文化人の中にあります。一方、奄美の方にも、「観光や振興策で潤う沖縄と合併できたらいい」(奄美のマスコミ関係者)という声があります。ところが、奄美の行政幹部は鹿児島系が主流で、沖縄合併論はタブーなのだそうです。きっと、奄美がヤマトに属することを証明する喜界島の発見は道州制の議論の中で鹿児島系の人たちに政治的に利用されるのでしょう。
世界一優しい声」として人気の歌手、中孝介や元ちとせ、「恵」「泉」「武」など奄美に一字の名字が多い(沖縄には一字はほとんどなく、三字が多い)のは、奄美出身とわかるように薩摩が採った政策だそうで、薩摩の一部には反薩摩感情もあります。一方、奄美は沖縄からも差別された歴史があるので、反沖縄感惰もあります。フォーラムに参加したある奄美出身の経済人は酒の席では「誰が沖縄の世話になんかなるか」とストレートに沖縄への反感を吐露していました。
佐野眞一氏の『沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史』には、奄美出身者が沖縄で受けたすさまじい差別の証言がいろいろと書かれてあり、読んでいてやりきれなくなります。那覇に住む奄美出身の知人も「基地問題で『日本人は沖縄を差別するなと言うのを聞くと『お前らがそんなこと言える立場か』と怒りがこみ上げる」と話していました。奄美諸島は沖縄より早く米国支配から解放され1953年に本土復帰しましたが、それにより沖縄で生活していた奄美出身者は「外国人」となり、選挙権がなくなったり、公職から追放されたりしました。奄美の人の沖縄に対する恨みは根深いものがあります。
沖縄では、文化人を中心に奄美との一体感が強張される一方で、「奄美なんてお荷物」と特に経済人は考えています。さらに、道州制で沖縄と九州が一緒になる構想について九州側からは「沖縄なんてお荷物を抱えたら、九州の財政が破たんする」(ある地方紙幹部)と拒否反応もあります。
地理的には「南西諸島」、歴史・文化圏としては「琉球弧」、思想的には奄美で暮らした作家島尾敏雄が唱えた「ヤポネシア」などの言葉でくくられる沖縄と奄美、沖縄には「琉球弧の先住民族会」という組織があります。「琉球弧の自立・独立」を掲げる「うるまネシア」という同人誌もあります。
国道58号線は那覇市から奄美、種子島、鹿児島市まで約600キロメートルの海上を挟んで結ぶロマンチックな道です。そんな兄弟のような沖縄と奄美でさえ、簡単には乗り越え難い溝があります。薩摩侵攻から400年、琉球処分から130年の節目の2OO9年。地域や民族の属性から離れて仲良くすることは本当に難しいことだと、つくづく思います。沖縄と本土の溝が簡単に埋まるわけがない、ましてパレスチナとユダヤが握手することの困難さは想像を絶するのだろう、などと思ってしまいます。
沖縄と宮古と八重山
沖縄は大きく、沖縄島(本島)宮古諸島、八重山諸島の3つに分かれ、それぞれ文化や言葉も違います。宮古と八重山を合わせて先島ということもあります。宮古や八重山の人は、本島に行くことを「沖縄に行く」と言います。これは、距離が離れているだけではなく、「沖縄本島とは同じではないという認識がある」(宮古島出身の経営者)と言います。
1609年に薩摩の支配を受けた琉球王朝は、人頭税を宮古と八重山に課します。貧富にかかわらず一律に上納が義務付けられるのですから、大変重い税です。宮古島には高さ143センチの「人頭税石」が今もあります。この身長になると人頭税がかけられたという説があるようです。この税制は琉球処分で沖縄県になった後の1903年にようやく廃止されます。2003年には東京・上野で「人頭税廃止100年コンサート」なるものが宮古出身の歌手らが参加して開かれていますから、怨みも重いようです。宮古に伝わる「アララガマ精神」(なにくそ、負けないぞ)は人頭税の歴史と結びついています。
与那国島西端の港町、久部良には「クブラバリ」という名所があります。断崖の上に3メートルほどの大きな岩の割れ目がある場所です。人頭税に苦しんだ島民は、人を減らすために、その割れ目を妊婦に飛ばしたというのです。体力のない母親はお腹の子供もろとも海の底に消えます。柵も何もないクブラバリの脇に立って穴をのぞくと、吸い込まれそうで足がすくみます。人頭税に苦しむ島民のために、首里の王朝に対し反乱を起こした石垣島の豪族オヤケアカハチは、今でも八重山の英雄です。
八重山の中心、石垣島の近くに浮かぶ竹富島の民謡「安里屋ユンタ」は、今ではすっかり沖縄を代表する唄になっています。「サァ 君は野中の茨の花か」とか「沖縄よいとこ 一度はおいで」と唄われる歌詞は後から付けた新バージョンで、本来は「サァ 安里屋ぬ クヤマによ」と唄われる労働歌です。メロディも少し違います。島の美人クヤマが首里から来た役人の求婚を断った、その気高さを讃える唄と書われています。沖縄民謡は普通、琉球音階(レとラを抜いた5音階)ですが、この最も有名な安里屋ユンタは、日本音階(ファとシを抜いた5音階)で作曲されています。ピアノだと黒鍵だけで弾けます。君が代や蛍の光と同じ音階です。八重山民謡には、琉球音階に対する反発からか、日本音階の曲も多いといいます。石垣島出身のBEGlNのポーカル、比嘉栄昇さんに話を聞いたときも「僕はレラ抜き(琉球音階)を信用していないんです。自然にレラ抜きになることはあっても、意識的には使いません」と言っていました。
宮古や八重山の人と話をすると、本土にもいろいろな地域がありそれぞれの文化があるように、沖縄も決して一枚岩ではない、むしろ「合衆国」だと感じます。ちなみに、安里屋ユンタのサビで繰り返される「マタハーリヌ チンダラ カヌシヤマョ」(なんと愛しい人だろ)が、戦争の時に日本軍の兵隊たちには「死んだら神さまよ」と聞こえたため本土にも広まった、という説があるようですが、本当でしょうか。
過去も含めてあえて大雑把に図式化すると、米国→日本→沖縄→奄美・宮古・八重山といった加害と被害の重構造があり、その中で沖縄は「日本は沖縄を差別している」と言い、日本は「沖縄だって奄美や宮古を差別しているじゃないか」と言い返す構図があります。あまり生産的な会話ではないことは確かでしょう
【natsuさんより】<カーマスー虎 Ⅴ>
2011年06月21日
<カーマスー虎 Ⅴ>
女性に対して・・・
□ 恥ずかしい思いをさせる(二人きりの時ね)のは高等テクニックだが(笑)
□ 辱めるのは絶対にNG
・恥ずかしい→好奇心はあるがちょっと怖いこと
・辱める→女性として、人間としてプライドを傷つけられること
2つの内容はまったく違います。
ここでの問題は、女性はこの2つの内容は全く違うと感じるのだが
男性は”鈍感”で、分からない人も多いということ。
(だからこそ、この感度が高く、理解出来る男性はモテる)
女性に対して・・・
□ 恥ずかしい思いをさせる(二人きりの時ね)のは高等テクニックだが(笑)
□ 辱めるのは絶対にNG
・恥ずかしい→好奇心はあるがちょっと怖いこと
・辱める→女性として、人間としてプライドを傷つけられること
2つの内容はまったく違います。
ここでの問題は、女性はこの2つの内容は全く違うと感じるのだが
男性は”鈍感”で、分からない人も多いということ。
(だからこそ、この感度が高く、理解出来る男性はモテる)