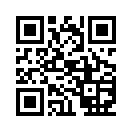神前にて謙る心の大切さ
2014年02月17日
そんなわけで、「「神に対する従順なる心・謙る心」についてです。
これを知るには、神道の祭典に参列されることが、一番の近道であると個人的には感じております。
実は今日も私は地元高千穂神社の大祭・祈年祭に参列させていただきました。
(知らない人も多いですが、神社には年に二回の大祭があり、春の祈念祭・秋の新嘗祭が大祭となります。
新聞で取りあげられていた紀元祭は中祭になるそうです。
紀元祭のときは体調不良で参加できなかったの・・・)
今日の祈念祭でも感じましたけれども、神職の皆様の立ち振る舞いの作法一つ一つに、
「神様への謙り・礼」が細やかにあらわされておられました。
たとえば、神道では、ご神前の正面にあたる真ん中は「正中」と言い、そこは神様の道になるので、
その位置にみだりに入ることは避けるべきとされています。
例外なく、祭式のときも、神主さんは正中を横切らねばならないときは、かならず恭しく頭を下げ、神様へのお詫びの気持ちを表しておられます。
また、神道では、神様に向かうときには、つねに左側を意識して使います。
宮司さんたちも、左足を先に出しておられます。
これは目上の方に対して「自分が謙っていること」をあらわしています。
お恥ずかしながら、神道にふれるまで、「上座・下座」(上座は右側・下座は左側)も知らなかった私には、
このような「敬いと謙りとしての礼」にふれ、心から打たれました。
そして、ご神前になるべくお尻を向けないように動いておられます。
明らかに、礼儀作法の素人からみても、神様を敬い、自らの謙りを行為にあらわして、
神様への礼を最大限に配慮していると分かる挙措をされています。
それは、人と人との関わりにも学ぶことができますけれども、
こちらが一歩引くという謙り、また相手様を一歩立てるという敬い、
その心遣いによって、人間関係はとてもスムーズにいきますよね。
ましてや神様からは、大いなる恩恵をいただいているのですから、
さらにさらに、その「敬いと謙り」をあらわしすぎるほどにあらわしてもまったく問題はないですし、
また、その「敬いと謙り」のお姿にふれることで、こちらも心を正すことができるという感化をいただくことができました。
このように「ご神前への敬いと謙り」としての礼の姿の大切さを知って、
自らの日頃の驕りを自覚し、自分から一歩謙ることの大切さを意識することができることに、
改めまして、神道という信仰と作法を築きあげてくださった祖霊に感謝すると共に、
自分の信仰にも諸神霊への非礼」があること自覚し、
もっと自分の信仰の姿勢についても、襟を正さなねばならないと感じます。
そして、これは、「謙りの姿勢」の重要さについての霊的エピソード。
数年前、ある本土からきたお客様(男性)を、奄美北部聖地の代表格・アマンデーにお連れしたことがあります。
その方はすごく全身から「やる気」をみなぎらせており、個人的には大変頼もしく感じておりました。
すると、その男性をアマンデーにお連れした瞬間・・・・
アマンデーの石碑の周り全体に、ものすごい殺気立った緊張感が走ったんです。
これには私もビックリしました。
(イメージでは、抜き身の刀を出した数十人の兵士に、切り捨てる気まんまんで取り囲まれた感じ)
今まで感じたことがない「いきなりレッドカード」状態に、でも男性はまったく気づいてないし、どうしてだとパニくりながらも、
瞬時にとらえたのは、
「この男性のやる気は、戦闘モードなんだ!」ということでした。
その男性の姿に、霊的に鎧を纏った姿が重なっているのを以前から感じていたのは事実ですが、
それが、「軍神の場所(古代の砦)」でもあるアマンデーでは、
「やる気モードのままでの参拝は、神様によってはケンカを売りにきたことと等しい」と気づいて愕然としました。
私はあわてて男性にお願いしました。
「すみません、どうぞアマンデーの神々にご挨拶の祈りをお願いいたします・・・・」
男性は私のガクブル感など分からないので、普通にお祈りをはじめてくださり、
お祈りの奏上に奄美の神々への感謝の言葉が朗々と響き渡ったときに、
その場の殺気がスゥーッとひいていく(刀をおさめてくれた)のを感じ、心から胸をなでおろしたことを思い出します。
これは、マジで怖かったです(笑)
でもこれですごく勉強になりました。
やる気というか、堂々とした姿勢というか、積極的姿勢そのものはすごく素晴らしいことなんですが、
ご神前では、やはり基本的に「謙りの姿勢」のほうが、誤解をまねかずにすむようです。
供物を捧げる・もしくは布施という行為も、神様への一番わかりやすい謙りなのかもしれません。
それから、私自身も、いろんな場所で参拝させていただくときは、いつもよりも敬いと謙りの心を第一の姿勢にして、恭しくお参りさせていただくように、特に気をつけております。
神様ご自身はともかく、その場所を護るお使いの方々にとっては、神様への無礼は罰の対象ですからね。
本当は、もっともっと、私達は
「従順」と「敬虔」を祈る姿勢において学ばねばならないなーと、感じます。