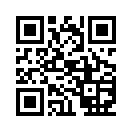栄西禅師について
2012年05月26日

栄西 : フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
永治元年4月20日 - 建保3年7月5日[1]
(1141年5月27日 - 1215年8月1日)
号 (道号)明庵
(房号)葉上房
諡号 千光国師
尊称 栄西禅師
生地 岡山
没地 鎌倉?・京都?
寺院 聖福寺・建仁寺
師 虚庵懐敞
著作 『誓願寺盂蘭盆縁起』・『喫茶養生記』・『興禅護国論』・『一代経論釈』
栄西(えいさい、ようさい)は、平安時代末期から鎌倉時代初期の僧である。明菴 栄西(みんなん えいさい、みんなん ようさい)とも呼ばれる。臨済宗の開祖、建仁寺の開山。天台密教葉上流の流祖。また、喫茶の習慣を日本に伝えたことでも知られる。
生年には異説がある。生地は備中国賀陽郡(岡山県加陽郡は現在加賀郡吉備中央町)。
経歴
永治元年(1141年)吉備津神社の権禰宜賀陽貞遠の子として誕生。曽祖父は薩摩守貞政。誕生地は、賀陽町(現岡山県加賀郡吉備中央町上竹)という説もある。
『紀氏系図』(『続群書類従』本)には異説として紀季重の子・重源の弟とする説を載せているが、これは重源が吉備津宮の再興に尽くしたことや重源が務めていた東大寺勧進職を栄西が継いだことから生じた説であり、史実ではないと考えられている。
久安4年(1148年) 8歳で『倶舎論』、『婆沙論』を読んだと伝えられる。
久寿元年(1154年) 14歳で比叡山延暦寺にて出家得度。
以後、延暦寺、吉備安養寺、伯耆大山寺などで天台宗の教学と密教を学ぶ。行法に優れ、自分の坊号を冠した葉上流を興す。
仁安3年(1168年) 形骸化し貴族政争の具と堕落した日本天台宗を立て直すべく、平氏の庇護と期待を得て南宋に留学。天台山万年寺などを訪れ、『天台章疎』60巻を将来する。
当時、南宋では禅宗が繁栄しており、日本仏教の精神の立て直しに活用すべく、禅を用いることを決意し学ぶこととなった。
文治3年(1187年) 再び入宋。仏法辿流のためインド渡航を願い出るが許可されず、天台山万年寺の虚庵懐敞に師事。
建久2年(1191年) 虚庵懐敞より臨済宗黄龍派の嗣法の印可を受ける。同年、帰国。
福慧光寺、千光寺などを建立し、筑前、肥後を中心に布教に努める。
建久5年(1194年) 彼や大日房能忍の禅宗が盛んになり、天台宗からの排斥を受け、禅宗停止が宣下される。
建久6年(1195年) 博多に聖福寺を建立し、日本最初の禅道場とする。
同寺は後に後鳥羽天皇より「扶桑最初禅窟」の扁額を賜る。栄西は自身が真言宗の印信を受けるなど、既存勢力との調和、牽制を図った。
建久9年(1198年) 『興禅護国論』執筆。
禅が既存宗派を否定するものではなく、仏法復興に重要であることを説く。
京都での布教に限界を感じて鎌倉に下向し、幕府の庇護を得ようとした。
正治2年(1200年) 北条政子建立の寿福寺の住職に招聘。
建仁2年(1202年) 源頼家の外護により京都に建仁寺を建立。
建仁寺は禅・天台・真言の三宗兼学の寺であった。以後、幕府や朝廷の庇護を受け、禅宗の振興に努めた。
建永元年(1206年) 重源の後を受けて東大寺勧進職に就任。
建仁寺、京都市東山区建暦2年(1212年) 法印に叙任。
建保元年(1213年) 権僧正に栄進。
政治権力に追従する者と、栄西に執拗な批判が向けられたのは、従来の利権を利かせたい者による。よって栄西が幕府を動かし、大師号猟号運動を行ったことは、生前授号の前例が無いことを理由に退けられる。天台座主慈円は『愚管抄』で栄西を「増上慢の権化」と罵っているが、栄西の言動は、むしろ政争や貴族の増上慢に苦しむ庶民の救済と幸福を追求したからに相違ないことは、他の記録から明白である。
建保3年(1215年) 享年75(満74歳没)で病没。終焉の地はの2説がある。
他者からの栄西観 [編集]日本曹洞宗の開祖である道元は、入宋前に建仁寺で修行しており、師の明全を通じて栄西とは孫弟子の関係になるが、栄西を非常に尊敬し、夜の説法を集めた『正法眼蔵随聞記』では、「なくなられた僧正様は…」と、彼に関するエピソードを数回も披露している。なお、栄西と道元は直接会っていたかという問題は、最近の研究では会っていないとされる。
主な著作 [編集]『誓願寺盂蘭盆縁起』 - 栄西唯一の肉筆文書で国宝。福岡市西区の誓願寺に滞在した折書いたと見られ、現在も同寺が所蔵(九州国立博物館寄託)。
『喫茶養生記』 - 『喫茶養生記』は上下2巻からなり、上巻では茶の種類や抹茶の製法、身体を壮健にする喫茶の効用が説かれ、下巻では飲水(現在の糖尿病)、中風、不食、瘡、脚気の五病に対する桑の効用と用法が説かれている。このことから、茶桑経(ちゃそうきょう)という別称もある。書かれた年代ははっきりせず、一般には建保2年(1214年)に源実朝に献上したという「茶徳を誉むる所の書」を完本の成立とするが、定説はない。
_______
http://www.ffortune.net/social/people/nihon-kama/eisai.htm
栄西禅師(1141-1215)
日本に禅宗をもちらした栄西禅師は栄治元年(1141)に生まれ、建保3年(1215)
7月5日に亡くなりました。
禅とは仏教における瞑想の技法であり、釈迦の時代から重要な修行法として使
用されていました。釈迦が菩提樹の下で瞑想をして悟りに到達したのは有名な
話です。この禅を行うことをその中核に据えたのが禅宗であり、その歴史は一
般にインドから中国へやってきた達磨大師(6世紀)に始まります。
その後五祖弘忍のあとを正式には神秀が継いだものの弘忍自身は実はひときわ
大きな器を持つ慧能にも密かに衣鉢を与えます。弘忍は騒ぎを避けるため慧能
を南方に逃し、以後神秀の系統を北宗禅、慧能の系統を南宗禅といいます。そ
してその後の禅は南宗禅の系統が発展し、これにより慧能は六祖とされ慧能の
偉大さ故に「祖」を付けるのは慧能までとしています。
この慧能の弟子の行思の系統からやがて曹洞宗が、懐譲の系統からやがて臨済
宗が生まれました。日本の禅はこの臨済宗・曹洞宗と、江戸時代にインゲン豆
で知られる隠元禅師が伝えた黄檗宗、そして虚無僧で知られる普化宗がありま
す。黄檗と普化はいづれも臨済系の一派です。
栄西は岡山の吉備津宮の神官の家に生まれました。(この吉備津宮にしろ奈良
の石上神宮にしろ、こういう古い神社の周辺には偉大な宗教家を生む環境があ
るようにも思います。)14歳で比叡山に上がりその後2度にわたって中国に留
学。黄龍派の臨済を学びました。
帰国後、栄西は最初博多の聖福寺(1195)を拠点として活動を始めます。これは
当時京都では天台宗・真言宗の2大平安仏教の勢力が強く、この新しい仏教を
奉じた活動をすることはできなかった為です。そこである程度理解者が増える
と今度は、頼朝が開いた新幕府のお膝元・鎌倉へ赴き、ここで幕府の中核に働
きかけ北条政子の援助で寿福寺(1200)を建てることに成功。
そして更に幕府の庇護のもとでようやく京都に建仁寺(1205)を建て、以後栄西
は京都と鎌倉を頻繁に往復して、精力的な活動を続けます。この栄西の活動に
より、仏教には天台・真言以外にも色々あるのだということが人々に認識され、
以後の道元(曹洞宗),法然(浄土宗),親鸞(浄土真宗)らの活動を支える下地が形
成されることになります。
___________
興禅護国論 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
興禅護国論(こうぜんごこくろん)とは、鎌倉時代初期、日本に臨済宗を伝え広めた栄西による仏教書。栄西が禅の布教にあたったとき、南都北嶺より激しい攻撃が加えられたのに対し、禅宗の要目を論じた著作[1][2]。栄西にとっては主著にあたり、「日本における禅宗独立宣言の書」とも評価される[3]。
概要
明菴栄西建久9年(1198年)以前の成立と考えられる[2]。全3巻で、禅宗は決して天台宗の教えに違背するものではなく、根本的には対立・矛盾するものではないとして、仏典(経・律・論[注釈 1])において説かれる禅の本旨を述べた著作である[2][4]。仏道を追究して悟りを得ることのできる人の心の広大さを称える一文「大いなるかな、心(こころ)哉(や)」で始まり、全編は、第一「令法久住門」、第二「鎮護国家門」、第三「世人決疑門」、第四「古徳誠証門」、第五「宗派血脈門」、第六「典拠増進門」、第七「大綱歓参門」、第八「建立支目門」、第九「大国説話門」、第十「回向発願門」の10門に分けられる[1][2]。禅の普及に圧力をかける南都北嶺とくに山門(比叡山延暦寺)に対する弁明・反論と朝廷から布教の許可を得ることを目指して著述された。
建久6年(1195年)の『出家大綱』、元久元年(1204年)の『日本仏法中興願文』とならび、栄西の思想を知るのに重要な著作である[1]。原文は漢文で、巻首には筆者不明の栄西の伝記、巻後には栄西自身による『未来記』が付されている[3]。
著述の経緯と目的
建久2年(1191年)、2度目の渡宋を終えて南宋より帰国した栄西は、九州地方北部において、聖福寺(福岡市博多区)[注釈 2]をはじめ、徳門寺(福岡市西区宮浦)、東林寺(福岡市西区宮浦)、誓願寺(福岡市西区今津)、報恩寺 (福岡市東区香椎)、龍護山千光寺(福岡県久留米市)、智慧光寺(長崎県高来郡)、龍灯山千光寺(長崎県平戸市)、狗留孫山修善寺(山口県下関市)などを構えて禅の普及に尽力したが、建久5年(1194年)7月5日、日本達磨宗の大日房能忍らの摂津国三宝寺の教団とともに布教禁止の処分を受けた[2]。
いっぽう筑前国筥崎(福岡市東区)の良弁という人物[注釈 3]が、九州において禅に入門する人びとが増えたことを延暦寺講徒に訴え、栄西による禅の弘通を停止するよう朝廷にも働きかけたため、建久6年には関白の九条兼実は栄西を京に呼び出し、大舎人頭の職にあった白河仲資に「禅とは何か」を聴聞させ、大納言の葉室宗頼に対してはその傍聴の任にあたらせた。しかし、京の世界にあっては禅を受容することは難しいものと判断された[2]。
そこで、明菴栄西によって、禅に対する誤解を解き、最澄(伝教大師)の開いた天台宗の教学に背くものではないとして禅の主旨を明らかにしようとして著されたのが本書である。九州で著されたと考えられる[5]。栄西は、禅を興すことは王法護国をもたらす基礎となるべきものであるという自身の主張から、経典『仁王護国般若波羅密多経』の題号により『興禅護国論』と命名した[2][注釈 4]。
内容
上述の通り、本書は10門より構成されており、それぞれの内容は以下に示す通りである[1][2]。
第一「令法久住門」…仏法の命の源は戒にあり、戒律を守って清浄であるならば仏法は久住する。
第二「鎮護国家門」…般若(=禅宗)は戒を基本としており、禅宗を奉ずれば諸天はその国家を守護する。
第三「世人決疑門」…禅に対する無知や疑惑、いわれなき誹謗(禅は悟りのない禅定をするだけである、「空」だけを強調する誤った教義であるなど)に対する反論。偏執の世人に対する批判。
第四「古徳誠証門」…古来の仏僧は禅を修行したことの証拠。
第五「宗派血脈門」…仏の心印は途絶えることなく栄西に至っていること。
第六「典拠増進門」…諸経論のなかにおいても教外別伝・不立文字の教えが説かれていること。
第七「大綱歓参門」…禅は仏教の総体であり、諸宗の根本であるとして以心伝心の真義を明らかにし、禅宗の大要を示す。
第八「建立支目門」…禅宗の施設・規式・条件などを示し、宗教界の刷新改革と戒律の重要性を説く。
第九「大国説話門」…インド・中国における禅門について示す。
第十「回向発願門」…功徳を他にふり向ける心を発せさせることの重要性を示す。
栄西は、この書において、戒律をすべての仏法の基礎に位置づけるとの立場に立ち、禅宗はすべての仏道に通じていると述べて、念仏など他の行を実践するとしても禅を修めなければ悟りを得ることはできないとした。また、生涯を天台宗の僧として生きた栄西は、四宗兼学を説いた最澄の教えのうち、禅のみが衰退しているのは嘆かわしいことであるとし、禅宗を興して持戒の人を重く用い、そのことによって比叡山の教学を復興し、なおかつ国家を守護することができると説いた[2][6]。そして、禅宗に対する批判は、比叡山そのものを謗ることになると主張した。
この論を著述するにあたっては数多くの仏典が引用されており、引用にはすべて典拠を掲げて厳正を期している[2][3]。
なお、栄西の手になる『未来記』1編は、自身の死去50年後には日本で禅の隆盛が訪れんことを期待するというもので、これは、日本の天台僧覚阿も師事した中国の高僧、杭州霊隠寺の仏海禅師慧遠が宋の乾道9年(1173年、承安3年)に自身の入滅後20年には禅は日本に渡って興隆すると予見したことを踏まえ、自身の帰国はこれに適合することを訴えたうえで禅の将来への期待を示したものであった[2]。
刊本
刊本としては、
『大正新脩大蔵経』第80巻(大蔵出版、1924年-1934年)
『大正新脩大蔵経』第80巻(大正新脩大蔵経刊行会、1992年)ISBN 4804395806
『日本思想大系』第16巻「中世禅家の思想」(岩波書店、1972年)ASIN B000J9AKC0
『国訳禅宗叢書』第2輯第8巻(第一書房、1974年)ISBN 978-4-8042-0218-1
などに収載されている[2]。
脚注
注釈 [編集]1.^ この3つの仏典を総称して「三蔵」という。
2.^ 博多聖福寺は、後鳥羽上皇より「扶桑最初禅窟」の宸翰を賜っている。安国山聖福寺
3.^ 奈良時代の華厳宗の僧良弁とは別の人物である。
4.^ 仁王般若波羅蜜経は、法華経および金光明最勝王経とともに「護国三部経」と称された。
「龍神様が写りました✩」な写真を見つけたので
特別取材:信者さんXさん(元修験僧)の話 ~最後の相談 巡り合わせ
お骨は家に置いちゃダメだし身に付けちゃダメ、散骨もってのほか!
ある信者さんからのご相談 ~謎の体調不良とご家族の不調の原因
仏壇に直系以外の位牌ダメ・ゼッタイ
精神科医A先生のお話(前編)注・不定期なので後編はいつになるか不明
特別取材:信者さんXさん(元修験僧)の話 ~最後の相談 巡り合わせ
お骨は家に置いちゃダメだし身に付けちゃダメ、散骨もってのほか!
ある信者さんからのご相談 ~謎の体調不良とご家族の不調の原因
仏壇に直系以外の位牌ダメ・ゼッタイ
精神科医A先生のお話(前編)注・不定期なので後編はいつになるか不明
Posted by アマミちゃん(野崎りの) at 16:01│Comments(1)
│スピリチュアル
この記事へのコメント
初めまして。時々読ませて頂いております。
さて…
どうして急に、栄西禅師を…?
私の通う職場は、建仁寺のすぐ近くです。
あまりにも唐突な感じが致しましたので、
ついコメントを書き込んでしまいました。
さて…
どうして急に、栄西禅師を…?
私の通う職場は、建仁寺のすぐ近くです。
あまりにも唐突な感じが致しましたので、
ついコメントを書き込んでしまいました。
Posted by くをん at 2012年05月29日 01:01
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。