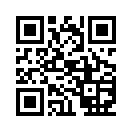思想の着地点はどこにあるか
2016年03月04日
また難しいテーマ振りやがって・・・ブツブツ・・・(笑)
さて、「思想の着地点はどこにあるか」という題をつけてみました。
世を啓蒙する思想は様々にありますが、
思想の違いによる反目は人類史にいまも戦争の陰りを落とし続けています。
では、まず『思想』とは何かについて。
ウィキペディアより。
思想
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%9D%E6%83%B3
思想(しそう、英: thought)とは、人間が自分自身および自分の周囲について、あるいは自分が感じ思考できるものごとについて抱く、あるまとまった考えのことである。
概要:
単なる直観とは区別され、感じた事(テーマ)を基に思索し、直観で得たものを反省的に洗練して言語・言葉としてまとめること。また、まとめたもの。哲学や宗教の一部との区分は曖昧である。なお、その時代が占める思想の潮流(時勢)のことを思潮と呼ぶ。
はい、思想の大まかな内容については分かりました。
では、思想とは、人類史においてどのような役割を果たしてきたのでしょうか?
主な思想をウィキより引用します。
西洋思想
ギリシャ神話
自然哲学
ソフィスト
ソクラテス、無知の知
プラトン、哲人政治
アリストテレス「人間はポリス的動物である」
エピクロス(エピクロス学派)
ゼノン(ストア学派)
ユダヤ教 ヤーヴェ 、『旧約聖書』
選民思想
モーゼの十戒
メシア思想
キリスト教 信仰の純粋性(原罪と罪の悔い改め)
アガペー(博愛主義)
福音書『新約聖書』
ミラノ勅令
キリスト教神学
教父哲学 三位一体説
アウグスティヌス
スコラ哲学 「哲学は神学の侍女」 トマス・アクィナス
ルネサンス、ヒューマニズム
懐疑主義、モラリスト ミシェル・ド・モンテーニュ (『随想録』、「われ何をか知る」)
ブレーズ・パスカル(『瞑想録』、「人間は考える葦である」)
宗教改革 マルティン・ルター
ジャン・カルヴァン
プロテスタンティズム
地動説
アイザック・ニュートン
イギリス経験論 フランシス・ベーコン『ノーヴムオルガーヌム(新機関)』 帰納法「知識は力なり」
イドラ
社会契約説 トマス・ホッブズ 『リヴァイアサン』、「万人の万人に対する闘争」
ジョン・ロック 生得観念批判、タブラ・ラーサ(白紙状態)
『統治論』、抵抗権
コモンロー エドワード・コーク卿 法の支配、『イギリス法提要』、「国王といえども神と法の下にある」
ウィリアム・ブラックストン 『イギリス法釈義』、ホイッグ史観
大陸合理論 ルネ・デカルト 『方法序説』、演繹法、普遍数学
方法的懐疑、「我思う、ゆえに我あり」
物心二元論
バールーフ・デ・スピノザ 『エティカ』、汎神論、「神即自然」
ゴットフリート・ライプニッツ 『単子論』、モナド
フランス 啓蒙思想
百科全書派
ジャン=ジャック・ルソー 『人間不平等起源論』、「自然に帰れ」
『社会契約論』、一般意志の実現
『エミール』
アレクシス・ド・トクヴィル 『アメリカの民主政治』
イギリス スコットランド啓蒙派 デイヴィッド・ヒューム 『人間本性論』
アダム・スミス 『道徳情操論』
近代保守主義 エドマンド・バーク 『フランス革命の省察』
ジョン・アクトン 「権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する」
アメリカ フェデラリスト アレクサンダー・ハミルトン
ジェームズ・マディソン 『ザ・フェデラリスト』
ドイツ ドイツ観念論 イマヌエル・カント 批判哲学
認識論のコペルニクス的転回
『純粋理性批判』、感性と悟性、「認識経験とともに始まる」
『実践理性批判』、実践理性、定言命法
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル 弁証法
人倫
歴史学派 フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー 歴史法学
フリードリッヒ・リスト 歴史経済学
功利主義 ジェレミ・ベンサム 「最大多数の最大幸福」
快楽計算、量的功利主義
ジョン・スチュアート・ミル 質的功利主義
プラグマティズム ジョン・デューイ 道具主義
社会主義(資本主義批判) カール・マルクス
フリードリヒ・エンゲルス
マルクス主義 唯物弁証法、唯物史観
階級闘争、社会主義革命
『資本論』『共産党宣言』
現代保守主義・自由主義リバタリアニズム フリードリヒ・ハイエク 『隷従への道』
マイケル・オークショット
カール・ポパー
ロバート・ノージック 『アナーキー・国家・ユートピア』
コミュニタリアニズム マイケル・サンデル
実存主義(ヘーゲル批判) セーレン・キェルケゴール『死に至る病』
フリードリヒ・ニーチェ ニヒリズム、「神は死んだ」
ルサンチマン
『力への意志』、永劫の回帰、運命愛
『ツァラトゥストラはかく語りき』、超人思想
マルティン・ハイデッガー 『存在と時間』、存在論的実存主義
カール・ヤスパース 限界状況
ジャン=ポール・サルトル 「実存は本質に先立つ」
アンガージュマン(社会参加)
構造主義(実存批判) ジークムント・フロイト(心理学) ジャック・ラカン(精神分析)
フェルディナン・ド・ソシュール(言語学) ロラン・バルト(記号学・文芸批評)
クロード・レヴィ=ストロース(人類学) ミシェル・フーコー(精神史)
ルイ・アルチュセール(認識論)
ポスト構造主義(構造批判) ジャック・デリダ
ジル・ドゥルーズ
フランクフルト学派(西洋啓蒙思想批判)
フェミニズム
東洋思想
『古事記』、『日本書紀』、八百万の神、アニミズム、シャーマニズム
仏教公伝、鎮護国家思想 聖徳太子『三経義疏』『憲法十七条』
聖武天皇、鑑真
行基
密教#日本の密教(現世志向、加持祈祷) 空海の真言宗(東密)、高野山金剛峰寺
最澄の天台宗(台密)、比叡山延暦寺
浄土信仰(来世志向、阿弥陀信仰) 融通念仏(良忍)、大念仏
鎌倉新仏教 浄土教(他力本願) 浄土宗(法然)、専修念仏(南無阿弥陀仏)
浄土真宗(親鸞)、悪人正機説
時宗(一遍)、踊念仏
禅宗(直示人心) 曹洞宗(道元)、只管打坐、身心脱落
臨済宗(栄西)
日蓮宗(日蓮)、「南無妙法蓮華経」、即身成仏・立正安国
儒学 朱子学 林羅山、理気説、湯島聖堂
新井白石、昌平坂学問所
尊王攘夷運動
陽明学
古学 山鹿素行(武士道)
伊藤仁斎、誠は道の全体なり(古義学)
荻生徂徠、先王の道(経世論)
国学 賀茂真淵(『万葉集』の研究、ますらおぶり)
本居宣長(『古事記』の研究、もののあはれ、古道に還る大和心)
蘭学(洋学) 『西洋記聞』、甘藷栽培、『解体新書』、蛮社の獄、和魂洋才
二宮尊徳(報徳思想)
「官民調和」(イギリス啓蒙思想) 明六社(『明六雑誌』) 森有礼、西周、加藤弘之
福澤諭吉 脱亜入欧
『学問のすゝめ』『文明論之概略』
独立自尊「一身独立して一国独立す」
実学、啓蒙思想家、教育者、慶應義塾
フランス民権思想 自由民権運動 植木枝盛
中江兆民『民約訳解』(回復的民権、恩賜的民権)、東洋のルソー
大正デモクラシー 吉野作造 民本主義
美濃部達吉 天皇機関説
女性解放運動 平塚雷鳥『青鞜』「元始、女性は実に太陽であった」
日本キリスト教史 内村鑑三(二つのJ、無教会主義)
新渡戸稲造
新島襄
日本の社会主義 河上肇
幸徳秋水(大逆事件)
大杉栄
日本の国家主義 平民主義 徳富蘇峰
国粋主義 陸羯南
平泉澄
山田孝雄
三宅雪嶺
上杉慎吉、「天皇主権説」
国家神道、教派神道 国体
教育勅語
国体明徴声明
超国家主義 北一輝(『日本改造法案大綱』)
アジア主義 大川周明
岡倉天心 「アジアはひとつ」
民俗学 柳田國男
西田幾多郎(『善の研究』)
和辻哲郎
55年体制
安保闘争
平和主義
戦後民主主義
日本国との平和条約
日本国憲法第9条
極東国際軍事裁判
象徴天皇制
諸子百家 儒家、士大夫、儒教 孔子 仁・礼
君子、徳治主義
孟子 性善説、仁義、四端・四徳、五倫
王道政治、易性革命
荀子(性悪説、礼知主義) 法家(韓非子;性善説批判、法治主義)
朱子学、格物致知
陽明学、知行合一
道家、老荘思想(老子、荘子)、道教 タオ(道)
無為自然(人為性批判)、小国寡民
墨家、墨子 兼愛交利説(「仁」の排他性を批判)
非攻説(平和主義)
上記引用はウィキからのものなので、私個人の選択は入っておりません。(笑)
このように、おおまかな思想を見てみると、思想とは社会秩序や共同体・民族・国家に大きな共通概念や方向性を与えるものであったことがわかります。
また、思想とは宗教的なものや社会運動的なるものも多く含み、結果として思想の違いによる相克はいまも数多く見つけられます。
では、この思想という、共同体に大きな影響を与えうる概念における、
共通の着地点とはどこにあるのでしょうか?
それには、思想というものが「多くの共同体や民族・国家に大きな方向性を与えうるもの」という影響性を詳細に理解することからはじまるのではないでしょうか。
影響とは大きな作用・反作用を含みます。
この作用・反作用をシュミレートし、この思想がより多くの個人や共同体への向上や繁栄・幸福に益する作用をもたらすか、
また、この思想における反作用(ネガティブなる影響や問題点)とは何かを分析し、
反作用に対してはどのようなフォローが必要であるのか、
それらを認識することによって、
「この思想はどのような方向性に個人や共同体を導くのか」
という理解をより緻密に行っていくこと。
世に様々なる思想は溢れておりますけれども、
思想の違いをもって反目や争いに至る前に、
「思想とはどのようなものであるのか、また、どのような正負の属性を持つのか」
を冷静に理解し把握しておくこと。
これが、思想の着地点であり、またさらなる再飛躍につながるのではないかと私は思います。
思想の着地点とは、特定の思想にのみ依拠し他の思想を排除するのではなく、
様々なる異なる思想を理解し、異なる思想の個性を尊重し、
理解の上に新たなる思想の潮流を創っていくこと。
より多くの理想や幸福に与する思想を、その都度に提示していく変革と創造。
これが、思想の着地点ではないかと、私は思います。
な・・・内容がカタイ・・・・。
さて、「思想の着地点はどこにあるか」という題をつけてみました。
世を啓蒙する思想は様々にありますが、
思想の違いによる反目は人類史にいまも戦争の陰りを落とし続けています。
では、まず『思想』とは何かについて。
ウィキペディアより。
思想
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%9D%E6%83%B3
思想(しそう、英: thought)とは、人間が自分自身および自分の周囲について、あるいは自分が感じ思考できるものごとについて抱く、あるまとまった考えのことである。
概要:
単なる直観とは区別され、感じた事(テーマ)を基に思索し、直観で得たものを反省的に洗練して言語・言葉としてまとめること。また、まとめたもの。哲学や宗教の一部との区分は曖昧である。なお、その時代が占める思想の潮流(時勢)のことを思潮と呼ぶ。
はい、思想の大まかな内容については分かりました。
では、思想とは、人類史においてどのような役割を果たしてきたのでしょうか?
主な思想をウィキより引用します。
西洋思想
ギリシャ神話
自然哲学
ソフィスト
ソクラテス、無知の知
プラトン、哲人政治
アリストテレス「人間はポリス的動物である」
エピクロス(エピクロス学派)
ゼノン(ストア学派)
ユダヤ教 ヤーヴェ 、『旧約聖書』
選民思想
モーゼの十戒
メシア思想
キリスト教 信仰の純粋性(原罪と罪の悔い改め)
アガペー(博愛主義)
福音書『新約聖書』
ミラノ勅令
キリスト教神学
教父哲学 三位一体説
アウグスティヌス
スコラ哲学 「哲学は神学の侍女」 トマス・アクィナス
ルネサンス、ヒューマニズム
懐疑主義、モラリスト ミシェル・ド・モンテーニュ (『随想録』、「われ何をか知る」)
ブレーズ・パスカル(『瞑想録』、「人間は考える葦である」)
宗教改革 マルティン・ルター
ジャン・カルヴァン
プロテスタンティズム
地動説
アイザック・ニュートン
イギリス経験論 フランシス・ベーコン『ノーヴムオルガーヌム(新機関)』 帰納法「知識は力なり」
イドラ
社会契約説 トマス・ホッブズ 『リヴァイアサン』、「万人の万人に対する闘争」
ジョン・ロック 生得観念批判、タブラ・ラーサ(白紙状態)
『統治論』、抵抗権
コモンロー エドワード・コーク卿 法の支配、『イギリス法提要』、「国王といえども神と法の下にある」
ウィリアム・ブラックストン 『イギリス法釈義』、ホイッグ史観
大陸合理論 ルネ・デカルト 『方法序説』、演繹法、普遍数学
方法的懐疑、「我思う、ゆえに我あり」
物心二元論
バールーフ・デ・スピノザ 『エティカ』、汎神論、「神即自然」
ゴットフリート・ライプニッツ 『単子論』、モナド
フランス 啓蒙思想
百科全書派
ジャン=ジャック・ルソー 『人間不平等起源論』、「自然に帰れ」
『社会契約論』、一般意志の実現
『エミール』
アレクシス・ド・トクヴィル 『アメリカの民主政治』
イギリス スコットランド啓蒙派 デイヴィッド・ヒューム 『人間本性論』
アダム・スミス 『道徳情操論』
近代保守主義 エドマンド・バーク 『フランス革命の省察』
ジョン・アクトン 「権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する」
アメリカ フェデラリスト アレクサンダー・ハミルトン
ジェームズ・マディソン 『ザ・フェデラリスト』
ドイツ ドイツ観念論 イマヌエル・カント 批判哲学
認識論のコペルニクス的転回
『純粋理性批判』、感性と悟性、「認識経験とともに始まる」
『実践理性批判』、実践理性、定言命法
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル 弁証法
人倫
歴史学派 フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー 歴史法学
フリードリッヒ・リスト 歴史経済学
功利主義 ジェレミ・ベンサム 「最大多数の最大幸福」
快楽計算、量的功利主義
ジョン・スチュアート・ミル 質的功利主義
プラグマティズム ジョン・デューイ 道具主義
社会主義(資本主義批判) カール・マルクス
フリードリヒ・エンゲルス
マルクス主義 唯物弁証法、唯物史観
階級闘争、社会主義革命
『資本論』『共産党宣言』
現代保守主義・自由主義リバタリアニズム フリードリヒ・ハイエク 『隷従への道』
マイケル・オークショット
カール・ポパー
ロバート・ノージック 『アナーキー・国家・ユートピア』
コミュニタリアニズム マイケル・サンデル
実存主義(ヘーゲル批判) セーレン・キェルケゴール『死に至る病』
フリードリヒ・ニーチェ ニヒリズム、「神は死んだ」
ルサンチマン
『力への意志』、永劫の回帰、運命愛
『ツァラトゥストラはかく語りき』、超人思想
マルティン・ハイデッガー 『存在と時間』、存在論的実存主義
カール・ヤスパース 限界状況
ジャン=ポール・サルトル 「実存は本質に先立つ」
アンガージュマン(社会参加)
構造主義(実存批判) ジークムント・フロイト(心理学) ジャック・ラカン(精神分析)
フェルディナン・ド・ソシュール(言語学) ロラン・バルト(記号学・文芸批評)
クロード・レヴィ=ストロース(人類学) ミシェル・フーコー(精神史)
ルイ・アルチュセール(認識論)
ポスト構造主義(構造批判) ジャック・デリダ
ジル・ドゥルーズ
フランクフルト学派(西洋啓蒙思想批判)
フェミニズム
東洋思想
『古事記』、『日本書紀』、八百万の神、アニミズム、シャーマニズム
仏教公伝、鎮護国家思想 聖徳太子『三経義疏』『憲法十七条』
聖武天皇、鑑真
行基
密教#日本の密教(現世志向、加持祈祷) 空海の真言宗(東密)、高野山金剛峰寺
最澄の天台宗(台密)、比叡山延暦寺
浄土信仰(来世志向、阿弥陀信仰) 融通念仏(良忍)、大念仏
鎌倉新仏教 浄土教(他力本願) 浄土宗(法然)、専修念仏(南無阿弥陀仏)
浄土真宗(親鸞)、悪人正機説
時宗(一遍)、踊念仏
禅宗(直示人心) 曹洞宗(道元)、只管打坐、身心脱落
臨済宗(栄西)
日蓮宗(日蓮)、「南無妙法蓮華経」、即身成仏・立正安国
儒学 朱子学 林羅山、理気説、湯島聖堂
新井白石、昌平坂学問所
尊王攘夷運動
陽明学
古学 山鹿素行(武士道)
伊藤仁斎、誠は道の全体なり(古義学)
荻生徂徠、先王の道(経世論)
国学 賀茂真淵(『万葉集』の研究、ますらおぶり)
本居宣長(『古事記』の研究、もののあはれ、古道に還る大和心)
蘭学(洋学) 『西洋記聞』、甘藷栽培、『解体新書』、蛮社の獄、和魂洋才
二宮尊徳(報徳思想)
「官民調和」(イギリス啓蒙思想) 明六社(『明六雑誌』) 森有礼、西周、加藤弘之
福澤諭吉 脱亜入欧
『学問のすゝめ』『文明論之概略』
独立自尊「一身独立して一国独立す」
実学、啓蒙思想家、教育者、慶應義塾
フランス民権思想 自由民権運動 植木枝盛
中江兆民『民約訳解』(回復的民権、恩賜的民権)、東洋のルソー
大正デモクラシー 吉野作造 民本主義
美濃部達吉 天皇機関説
女性解放運動 平塚雷鳥『青鞜』「元始、女性は実に太陽であった」
日本キリスト教史 内村鑑三(二つのJ、無教会主義)
新渡戸稲造
新島襄
日本の社会主義 河上肇
幸徳秋水(大逆事件)
大杉栄
日本の国家主義 平民主義 徳富蘇峰
国粋主義 陸羯南
平泉澄
山田孝雄
三宅雪嶺
上杉慎吉、「天皇主権説」
国家神道、教派神道 国体
教育勅語
国体明徴声明
超国家主義 北一輝(『日本改造法案大綱』)
アジア主義 大川周明
岡倉天心 「アジアはひとつ」
民俗学 柳田國男
西田幾多郎(『善の研究』)
和辻哲郎
55年体制
安保闘争
平和主義
戦後民主主義
日本国との平和条約
日本国憲法第9条
極東国際軍事裁判
象徴天皇制
諸子百家 儒家、士大夫、儒教 孔子 仁・礼
君子、徳治主義
孟子 性善説、仁義、四端・四徳、五倫
王道政治、易性革命
荀子(性悪説、礼知主義) 法家(韓非子;性善説批判、法治主義)
朱子学、格物致知
陽明学、知行合一
道家、老荘思想(老子、荘子)、道教 タオ(道)
無為自然(人為性批判)、小国寡民
墨家、墨子 兼愛交利説(「仁」の排他性を批判)
非攻説(平和主義)
上記引用はウィキからのものなので、私個人の選択は入っておりません。(笑)
このように、おおまかな思想を見てみると、思想とは社会秩序や共同体・民族・国家に大きな共通概念や方向性を与えるものであったことがわかります。
また、思想とは宗教的なものや社会運動的なるものも多く含み、結果として思想の違いによる相克はいまも数多く見つけられます。
では、この思想という、共同体に大きな影響を与えうる概念における、
共通の着地点とはどこにあるのでしょうか?
それには、思想というものが「多くの共同体や民族・国家に大きな方向性を与えうるもの」という影響性を詳細に理解することからはじまるのではないでしょうか。
影響とは大きな作用・反作用を含みます。
この作用・反作用をシュミレートし、この思想がより多くの個人や共同体への向上や繁栄・幸福に益する作用をもたらすか、
また、この思想における反作用(ネガティブなる影響や問題点)とは何かを分析し、
反作用に対してはどのようなフォローが必要であるのか、
それらを認識することによって、
「この思想はどのような方向性に個人や共同体を導くのか」
という理解をより緻密に行っていくこと。
世に様々なる思想は溢れておりますけれども、
思想の違いをもって反目や争いに至る前に、
「思想とはどのようなものであるのか、また、どのような正負の属性を持つのか」
を冷静に理解し把握しておくこと。
これが、思想の着地点であり、またさらなる再飛躍につながるのではないかと私は思います。
思想の着地点とは、特定の思想にのみ依拠し他の思想を排除するのではなく、
様々なる異なる思想を理解し、異なる思想の個性を尊重し、
理解の上に新たなる思想の潮流を創っていくこと。
より多くの理想や幸福に与する思想を、その都度に提示していく変革と創造。
これが、思想の着地点ではないかと、私は思います。
な・・・内容がカタイ・・・・。
大アジア主義の復活と日本の使命についてのつぶやき(過去記事を加筆・修正)
2016年03月04日
これまでの私自身の流れを見ると、「大アジア主義」が一つのキーワードではないかと感じる。
小日向白朗も大アジア主義でした。(笑)
これまで私が注目してきたり、もしくはご縁のあったりした方々は
三島由紀夫、
松井石根、
広田弘毅、
北一輝(北については私はそこまで注目してないけど数人の方から関わりを指摘された)、
安川敬一郎、
頭山満、
すべて「大アジア主義」だったんですね。
A級戦犯とされた七柱の英霊の御魂を祀る殉国七士廟。
そのご遺骨は、松井石根大将が生前祀られていた「興亜観音」に長年隠されていたものを分骨されたものです。
松井石根大将が祀っていた「興亜観音」こそ、
日本とアジアの相克を修復させ、日本が掲げた「八紘一宇・五族協和の理想」の正当性を日本と世界に知らしめる重要なキーだと私は思っておりました。
そんな中、第二回惠隆之介奄美講演会をさせていただいて、お近づきになれた隊友会の方のお宅に、
頭山満の掛け軸を見つけたときには、もう飛び上がりそうになったわけです。
全部つながっとるがな(笑)
また、訪れた殉国七士廟で、聞こえてきた「広田弘毅」の名前。
調べてみると、玄洋社の社員でした(笑)
つまり頭山満の弟子でした(笑)
そして、松井石根も大アジア主義者だったww
うーん。福岡が熱いぞ!!!(頭山満と広田弘毅は福岡出身)
はい、そして、私のブログのはるか数年前に出てきたこの方。
そう、北九州いのちのたび博物館にいらしたあの方です。
安川敬一郎
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%B7%9D%E6%95%AC%E4%B8%80%E9%83%8E
この人、玄洋社のスポンサーだったんじゃん!!!!!
ギャー!!!!
全部つながりすぎててガクブル・・・・・
(ちなみに松井石根は愛知県名古屋市出身ね)
はい、ここからは私の根拠のないイメージです。(笑)
この明治維新直後から戦中にかけての大アジア主義こそ、
まだ明らかにされていない、ムー文明の継承文明としての上古代日本が、
東アジア全土に文明をもたらし、アジアの中心として中国沿岸部までも統治していた当時の思想の、
その復興運動ではなかったかと思うのです。
ただ、上古代における「大東亜共栄圏」とは、欧米列強への対抗を主眼においたものではなく、
「盟主日本のもとに、日本の文化の力によって周辺諸国を豊かにしていく」
という、あくまでも周辺諸国も含めた共存共栄を目的としたゆるやかな連合体ではなかったでしょうか。
これってヘルメス型統治ともつながるのよね。
上古代において盟主日本にあった思想は、「道教」として中国大陸にも受け継がれたと私は推測しています。
道教こそ当時の倭国にあった「元なる神」への信仰であったのではないかと私は考えております。
(つまり天帝とは「元なる神」であり、その代理人がアマカミ(天皇)だったと思うの)
だって、おかしいと思いません?あの道教の世界観。
あれ、四海がないと成り立たないんですよ。
四方が海で囲まれてる国発祥の教えでしょうよどうみてもwww
そして、中国の道教の導師複数が「道教の教えははるか古代に日本からきたもの」と明言しています。
はるか数千年前に、「大東亜共栄圏」を実現していた上古代日本の、
その復興運動としての、大アジア主義。
その大アジア主義による日中融和の理想を引き裂いたのは誰か。誰が日中戦争を起こさせてしまったのか。
また、何がそこに足りなかったのか。
現代において「上古代大東亜共栄圏」を復活させるならば、それはどのような形であるべきか。
その問いと答えを、奄美大島そして南西諸島は見つける必要があると私は思います。
日本と中国を繋ぎ、日本とアジアを繋ぎ、日本と世界を繋ぐための「共栄」の理想。
これは、日本がリーダー(盟主)となるときにはじめて可能になるのではないでしょうか?
そのためにも、強い日本、そして今ふたたびのリーダーたる日本、徳ある日本を創る必要があるのではないかと、
私は思います。
奄美そして南西諸島が、そのための導き手とならんことを願います。
間違っても中国の傀儡にならぬように。(翁長さん、あなたのことよ)
奄美大島が上古代においてどのような位置づけだったかは分かりませんが、
皇居の神殿ではいまだに一族継承の女性神官しか立ち入りが許されない神域があるということと、
伊勢神宮で今も守られる倭姫(斎王・祭主)という存在から鑑みて、
神道に女性神官をのこしたなんらかの霊的作法・宗教観の源流が、奄美にあるのではないかと私は空想しております。
という妄想でした。(笑)
妄想だぞ妄想!
あくまでも戯言として聞き流すように!!!!(笑)
そして、この上古代大東亜共栄圏の理念を最も近い時代において実践しようとした方こそ、
私は、神武天皇その方ではなかったかと思う。
それは国津神と言われる各地の豪族を、天津神信仰という宗教(共通理念)によって再統合・統治する試みであり、「大和朝廷」による共栄のためのゆるやかな諸国連合成立であったのだと思うのですね。
(おそらく神武天皇自体には盟主としての権威はあれど各地方の豪族をすべて実質支配できるような武力も実権もなかったであろうと思われる。
長髄彦との戦争に勝ったあとに橿原に朝廷をつくることができたのは、神武天皇による「統治における徳」が各地の豪族に認められたのが大きかったのではないだろうか?)
うーん、まだまだ勉強不足だ。
とりあえず蒋介石がいたら殴りたいです。
小日向白朗も大アジア主義でした。(笑)
これまで私が注目してきたり、もしくはご縁のあったりした方々は
三島由紀夫、
松井石根、
広田弘毅、
北一輝(北については私はそこまで注目してないけど数人の方から関わりを指摘された)、
安川敬一郎、
頭山満、
すべて「大アジア主義」だったんですね。
A級戦犯とされた七柱の英霊の御魂を祀る殉国七士廟。
そのご遺骨は、松井石根大将が生前祀られていた「興亜観音」に長年隠されていたものを分骨されたものです。
松井石根大将が祀っていた「興亜観音」こそ、
日本とアジアの相克を修復させ、日本が掲げた「八紘一宇・五族協和の理想」の正当性を日本と世界に知らしめる重要なキーだと私は思っておりました。
そんな中、第二回惠隆之介奄美講演会をさせていただいて、お近づきになれた隊友会の方のお宅に、
頭山満の掛け軸を見つけたときには、もう飛び上がりそうになったわけです。
全部つながっとるがな(笑)
また、訪れた殉国七士廟で、聞こえてきた「広田弘毅」の名前。
調べてみると、玄洋社の社員でした(笑)
つまり頭山満の弟子でした(笑)
そして、松井石根も大アジア主義者だったww
うーん。福岡が熱いぞ!!!(頭山満と広田弘毅は福岡出身)
はい、そして、私のブログのはるか数年前に出てきたこの方。
そう、北九州いのちのたび博物館にいらしたあの方です。
安川敬一郎
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%B7%9D%E6%95%AC%E4%B8%80%E9%83%8E
この人、玄洋社のスポンサーだったんじゃん!!!!!
ギャー!!!!
全部つながりすぎててガクブル・・・・・
(ちなみに松井石根は愛知県名古屋市出身ね)
はい、ここからは私の根拠のないイメージです。(笑)
この明治維新直後から戦中にかけての大アジア主義こそ、
まだ明らかにされていない、ムー文明の継承文明としての上古代日本が、
東アジア全土に文明をもたらし、アジアの中心として中国沿岸部までも統治していた当時の思想の、
その復興運動ではなかったかと思うのです。
ただ、上古代における「大東亜共栄圏」とは、欧米列強への対抗を主眼においたものではなく、
「盟主日本のもとに、日本の文化の力によって周辺諸国を豊かにしていく」
という、あくまでも周辺諸国も含めた共存共栄を目的としたゆるやかな連合体ではなかったでしょうか。
これってヘルメス型統治ともつながるのよね。
上古代において盟主日本にあった思想は、「道教」として中国大陸にも受け継がれたと私は推測しています。
道教こそ当時の倭国にあった「元なる神」への信仰であったのではないかと私は考えております。
(つまり天帝とは「元なる神」であり、その代理人がアマカミ(天皇)だったと思うの)
だって、おかしいと思いません?あの道教の世界観。
あれ、四海がないと成り立たないんですよ。
四方が海で囲まれてる国発祥の教えでしょうよどうみてもwww
そして、中国の道教の導師複数が「道教の教えははるか古代に日本からきたもの」と明言しています。
はるか数千年前に、「大東亜共栄圏」を実現していた上古代日本の、
その復興運動としての、大アジア主義。
その大アジア主義による日中融和の理想を引き裂いたのは誰か。誰が日中戦争を起こさせてしまったのか。
また、何がそこに足りなかったのか。
現代において「上古代大東亜共栄圏」を復活させるならば、それはどのような形であるべきか。
その問いと答えを、奄美大島そして南西諸島は見つける必要があると私は思います。
日本と中国を繋ぎ、日本とアジアを繋ぎ、日本と世界を繋ぐための「共栄」の理想。
これは、日本がリーダー(盟主)となるときにはじめて可能になるのではないでしょうか?
そのためにも、強い日本、そして今ふたたびのリーダーたる日本、徳ある日本を創る必要があるのではないかと、
私は思います。
奄美そして南西諸島が、そのための導き手とならんことを願います。
間違っても中国の傀儡にならぬように。(翁長さん、あなたのことよ)
奄美大島が上古代においてどのような位置づけだったかは分かりませんが、
皇居の神殿ではいまだに一族継承の女性神官しか立ち入りが許されない神域があるということと、
伊勢神宮で今も守られる倭姫(斎王・祭主)という存在から鑑みて、
神道に女性神官をのこしたなんらかの霊的作法・宗教観の源流が、奄美にあるのではないかと私は空想しております。
という妄想でした。(笑)
妄想だぞ妄想!
あくまでも戯言として聞き流すように!!!!(笑)
そして、この上古代大東亜共栄圏の理念を最も近い時代において実践しようとした方こそ、
私は、神武天皇その方ではなかったかと思う。
それは国津神と言われる各地の豪族を、天津神信仰という宗教(共通理念)によって再統合・統治する試みであり、「大和朝廷」による共栄のためのゆるやかな諸国連合成立であったのだと思うのですね。
(おそらく神武天皇自体には盟主としての権威はあれど各地方の豪族をすべて実質支配できるような武力も実権もなかったであろうと思われる。
長髄彦との戦争に勝ったあとに橿原に朝廷をつくることができたのは、神武天皇による「統治における徳」が各地の豪族に認められたのが大きかったのではないだろうか?)
うーん、まだまだ勉強不足だ。
とりあえず蒋介石がいたら殴りたいです。