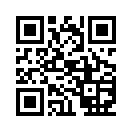【子房さん】ルネサンスとは
2012年08月18日
ルネサンスとは 2012年8月16日 22:41
中世キリスト教圏の特にイタリアを中心になされたもので、古典の復興とも言われています
なぜ古典かと言うと、中世ヨーロッパではキリスト教が絶大な権力をもって人々の上を蓋するように覆っていたわけです
キリスト教では人間は原罪を背負った存在とされていますので、個人の自由や権利などは尊重されないわけですね
つまり人間はほっておけば罪を重ねていくだめな奴だっと考えられていたので、罪から救済できる力を持っている教会が、人々を支配していたのです
すると、社会はたいへん窮屈になり、人々は抑圧されてしまいますので、息苦しいわけです
すると、キリスト教が社会を覆う以前の古典にある人々の自由さに憧れますね
それゆえ、ルネッサンスでは古典に触発された人々によって、もっと自由を求めて現れたものだと言えます
そのルネッサンスを決定づけるといいますか、一番の核になったものが、ヘルメス主義だと私は思います
こんなことはよそでは書いていませんので、あくまで私の解釈です
ヘルメス主義については何度も日記に書いてきました
キリスト教の原罪思想や、その母体となったユダヤ教などからは、人間は罪を犯す奴らで、価値の低いものという考え方が導かれてくるわけですが、ヘルメス主義では、人間の本質は神様と同質と考えますので、人間を尊重する思想が出て来ます
ですので、中世ヨーロッパの抑圧てきな教会の支配や思想に対して、人間を尊重する思想をうちに含んだルネッサンスが、ヘルメス主義をもとにして開花したのだと思います
現代の政治でも、人々を抑圧する方向にある社会主義や共産主義があり、一方で人権を尊重して自由を尊重する自由主義、資本主義の対立があるわけですが、
個人としての人間の価値をあまり尊重しない思想(中世キリスト教)と、人間の価値を尊重する思想(ヘルメス主義)があって、対立していたわけです
詳しくはヘルメス主義についての日記を参照ください
そのルネッサンスの流れからキリスト教のなかでもプロテスタントなどの新教が発生してきたのでしょう
(アマミキョ注・子房さんはミクシィで日記を書いておられますので、興味のある方は、子房さんの日記の過去ログをご参照ください)
中世キリスト教圏の特にイタリアを中心になされたもので、古典の復興とも言われています
なぜ古典かと言うと、中世ヨーロッパではキリスト教が絶大な権力をもって人々の上を蓋するように覆っていたわけです
キリスト教では人間は原罪を背負った存在とされていますので、個人の自由や権利などは尊重されないわけですね
つまり人間はほっておけば罪を重ねていくだめな奴だっと考えられていたので、罪から救済できる力を持っている教会が、人々を支配していたのです
すると、社会はたいへん窮屈になり、人々は抑圧されてしまいますので、息苦しいわけです
すると、キリスト教が社会を覆う以前の古典にある人々の自由さに憧れますね
それゆえ、ルネッサンスでは古典に触発された人々によって、もっと自由を求めて現れたものだと言えます
そのルネッサンスを決定づけるといいますか、一番の核になったものが、ヘルメス主義だと私は思います
こんなことはよそでは書いていませんので、あくまで私の解釈です
ヘルメス主義については何度も日記に書いてきました
キリスト教の原罪思想や、その母体となったユダヤ教などからは、人間は罪を犯す奴らで、価値の低いものという考え方が導かれてくるわけですが、ヘルメス主義では、人間の本質は神様と同質と考えますので、人間を尊重する思想が出て来ます
ですので、中世ヨーロッパの抑圧てきな教会の支配や思想に対して、人間を尊重する思想をうちに含んだルネッサンスが、ヘルメス主義をもとにして開花したのだと思います
現代の政治でも、人々を抑圧する方向にある社会主義や共産主義があり、一方で人権を尊重して自由を尊重する自由主義、資本主義の対立があるわけですが、
個人としての人間の価値をあまり尊重しない思想(中世キリスト教)と、人間の価値を尊重する思想(ヘルメス主義)があって、対立していたわけです
詳しくはヘルメス主義についての日記を参照ください
そのルネッサンスの流れからキリスト教のなかでもプロテスタントなどの新教が発生してきたのでしょう
(アマミキョ注・子房さんはミクシィで日記を書いておられますので、興味のある方は、子房さんの日記の過去ログをご参照ください)
広田弘毅の前世について洪正幸さんにお聞きしてみた!
うちのブログで大変お世話になっております洪さん(子房さん)が、PHPから本をご出版されました!
明治維新の陰には奄美あり (子房さんのブログより転載)
子房さんが倉山満さんの前世をリーディングしてくださいました!
子房さんからいただいたヒーリング体験(過去記事)
STAP細胞はやはりあった!問われる批判者の立場 (子房さんブログより)
うちのブログで大変お世話になっております洪さん(子房さん)が、PHPから本をご出版されました!
明治維新の陰には奄美あり (子房さんのブログより転載)
子房さんが倉山満さんの前世をリーディングしてくださいました!
子房さんからいただいたヒーリング体験(過去記事)
STAP細胞はやはりあった!問われる批判者の立場 (子房さんブログより)
Posted by アマミちゃん(野崎りの) at 12:09│Comments(1)
│洪正幸さん(子房さん)
この記事へのコメント
ルネサンス根底にあるヘルメス思想は結構知られているようです。
面白い過去世探訪の話があります。
題名は「デジデリオ・ラビリンス」エッセイストののりやっこさんの実体験に基づく、イタリア過去世探訪のお話。
京都の霊能者の女性との話で、いろんな物がリンクしていく流れが面白い話でした.
ビーナスを描いたボッティチェルリは、ヘルメス思想に影響を受けていくつかの作品を残してますし、そういった絵画から類推する思想的背景は、
当時の流行を物語っているようですね。
錬金術への探求と言われがちですが、実際に当時の人が何故にその思想に
魅力を感じ、知識人たちのサロンで語られたのか、。ですよね。
キーワードはやはり「神秘」なんでしょうね~。
ただ、ボッティチェルリに関しては、作風の自由奔放さが批判の的になったことも手伝ったのか、キリスト教に準じた禁欲的な作風に変わってしまったそうです・・・
が、それらの作品はあまり有名にはなってないようですね。
面白い過去世探訪の話があります。
題名は「デジデリオ・ラビリンス」エッセイストののりやっこさんの実体験に基づく、イタリア過去世探訪のお話。
京都の霊能者の女性との話で、いろんな物がリンクしていく流れが面白い話でした.
ビーナスを描いたボッティチェルリは、ヘルメス思想に影響を受けていくつかの作品を残してますし、そういった絵画から類推する思想的背景は、
当時の流行を物語っているようですね。
錬金術への探求と言われがちですが、実際に当時の人が何故にその思想に
魅力を感じ、知識人たちのサロンで語られたのか、。ですよね。
キーワードはやはり「神秘」なんでしょうね~。
ただ、ボッティチェルリに関しては、作風の自由奔放さが批判の的になったことも手伝ったのか、キリスト教に準じた禁欲的な作風に変わってしまったそうです・・・
が、それらの作品はあまり有名にはなってないようですね。
Posted by きんぎょ at 2012年08月18日 19:26
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。