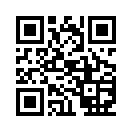宮本武蔵という偉人
2010年07月13日
隊長にすすめられて宮本武蔵を調べてみたら、ただ強いだけの剣豪じゃないことがよくわかりました。
強さはまさに「鬼神」の域でしたが、それに裏打ちされた思想があるんですね。
もはや剣聖ですね。
現代にも通じる言葉だと思います。
___________________
右一流の兵法の道、朝なゝゝ夕なゝゝ勤めおこなふによりて、おのづら広き心になつて、多分一分の兵法として世に伝ふる所、初而書顕はす事、地水火風空、是五巻也。我兵法を学ばんと思ふ人は道をおこなふ法あり。
第一によこしまになき事をおもふ所
第二に道の鍛錬する所
第三に諸芸にさはる所
第四に諸職の道を知る事
第五に物事の損徳をわきまゆる事
第六に諸事目利を仕覚ゆる事
第七に目に見えぬ所をさとつてしる事
第八にわづかなる事にも気を付くる事
第九に役にたたぬ事をせざる事
大形如此(おおかたかくのごとき)理を心にかけて兵法の道鍛錬すべき也。此道に限りて、直なる所を広く見たてざれば、兵法の達者とは成りがたし。此法を学び得ては一身にして二十三十の敵にもまくべき道にあらず。先づ気に兵法をたえさず、直なる道を勤めては、手にても打勝ち、目に見る事も人にかち、又鍛錬をもつて惣体自由(そうたいやわらか)なれば、身にても人に勝ち、又此道に慣れたる心なれば、心をもつても人に勝ち、此所に至りてはいかにとして人にまくる道あらんや。又大きなる兵法にしては、善人を持事にかち、人数をつかふ事にかち、身をただしくおこなふ道にかち、国を治むる事にかち、民をやしなふ事にかち、世の例法 をおこなひかち、いづれの道においても人にまけざる所をしりて、身をたすけ名をたすくる所、是兵法の道也。
正保二年五月十二日 新免武蔵
寛文七年二月五日 寺尾夢世勝延
山本源介殿
現代語訳
右の一流の兵法の道を朝に夕に鍛錬することで、自然と広い心になって、多人数対多人数、一対一の兵法として後世に伝えることを初めて書き表したのが、地水火風空の五巻である。兵法を学ぼうと思う人には、兵法を学ぶ掟がある。
第一 実直な正しい道を思うこと
第二 鍛錬すること
第三 様々な芸にふれること
第四 様々な職能を知ること
第五 物事の損得を知ること
第六 様々な事を見分ける力を養うこと
第七 目に見えないところを悟ること
第八 ちょっとしたことにも気をつけること
第九 役に立たないことはしないこと
だいたいこのようなことを心がけて、兵法の道を鍛錬すべきである。この道に限っては、広い視野に立って真実を見極めなければ兵法の達人にはなりがたい。これを会得すれば、一人でも20、30の敵にも負けないのである。まず、気持ちに兵法を忘れず、正しく一生懸命鍛錬すれば、まず手でも人に勝ち、見る目においても人に勝つことができる。 鍛錬の結果、体が自由自在になれば体でも人に勝ち、この道に心が慣れれば心でも人に勝つことができるのである。兵法を学んでこの境地にたどりついた時は、すべてにおいて人に負けることはありえない。また、集団の兵法では、有能な人を仲間に持つことで勝り、多くの人数を使うことに勝り、わが身を正すことで勝ち、国を治めることでも勝ち、民を養うことでも勝ち、世の秩序を保つことができる。何事においても人に負けないことを知って、身を助け名誉を守ることこそ、兵法の道である。
___________________
「空を道とし、道を空とみる。」
(意味)
ここでいう「道」とは、武士としての道を意味すると思われ、
「空」とは、「迷いのない心」「とらわれない心」の事。
つまり、「無欲、無心が事をなす」となります。
_________
「神仏を敬い、神仏に頼らず。」
(意味)
神仏に頼るのではなく、神仏の意にかなう心構え、
生活姿勢が大切。
__________
千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす。
_______________
武士といえば、常に死ができている者と自惚れているようだが、
そんなものは出家、女、百姓とて同様だ。
武士が他と異なるのは、兵法の心得があるという一点においてだけだ。
_____________
構えあって構えなし。
__________
打ち込む態勢をつくるのが先で、剣はそれに従うものだ
__________
勝負とは、敵を先手、先手と打ち負かしていくことであり、
構えるということは、敵の先手を待つ心にほかならない。
「構える」などという後手は邪道なのである。
____________
一生の間、欲心を思わず。
_________
平常の身体のこなし方を戦いのときの身のこなし方とし、
戦いのときの身のこなし方を平常と同じ身のこなし方とすること。
_____________
われ事において後悔せず。
_____________
強さはまさに「鬼神」の域でしたが、それに裏打ちされた思想があるんですね。
もはや剣聖ですね。
現代にも通じる言葉だと思います。
___________________
右一流の兵法の道、朝なゝゝ夕なゝゝ勤めおこなふによりて、おのづら広き心になつて、多分一分の兵法として世に伝ふる所、初而書顕はす事、地水火風空、是五巻也。我兵法を学ばんと思ふ人は道をおこなふ法あり。
第一によこしまになき事をおもふ所
第二に道の鍛錬する所
第三に諸芸にさはる所
第四に諸職の道を知る事
第五に物事の損徳をわきまゆる事
第六に諸事目利を仕覚ゆる事
第七に目に見えぬ所をさとつてしる事
第八にわづかなる事にも気を付くる事
第九に役にたたぬ事をせざる事
大形如此(おおかたかくのごとき)理を心にかけて兵法の道鍛錬すべき也。此道に限りて、直なる所を広く見たてざれば、兵法の達者とは成りがたし。此法を学び得ては一身にして二十三十の敵にもまくべき道にあらず。先づ気に兵法をたえさず、直なる道を勤めては、手にても打勝ち、目に見る事も人にかち、又鍛錬をもつて惣体自由(そうたいやわらか)なれば、身にても人に勝ち、又此道に慣れたる心なれば、心をもつても人に勝ち、此所に至りてはいかにとして人にまくる道あらんや。又大きなる兵法にしては、善人を持事にかち、人数をつかふ事にかち、身をただしくおこなふ道にかち、国を治むる事にかち、民をやしなふ事にかち、世の例法 をおこなひかち、いづれの道においても人にまけざる所をしりて、身をたすけ名をたすくる所、是兵法の道也。
正保二年五月十二日 新免武蔵
寛文七年二月五日 寺尾夢世勝延
山本源介殿
現代語訳
右の一流の兵法の道を朝に夕に鍛錬することで、自然と広い心になって、多人数対多人数、一対一の兵法として後世に伝えることを初めて書き表したのが、地水火風空の五巻である。兵法を学ぼうと思う人には、兵法を学ぶ掟がある。
第一 実直な正しい道を思うこと
第二 鍛錬すること
第三 様々な芸にふれること
第四 様々な職能を知ること
第五 物事の損得を知ること
第六 様々な事を見分ける力を養うこと
第七 目に見えないところを悟ること
第八 ちょっとしたことにも気をつけること
第九 役に立たないことはしないこと
だいたいこのようなことを心がけて、兵法の道を鍛錬すべきである。この道に限っては、広い視野に立って真実を見極めなければ兵法の達人にはなりがたい。これを会得すれば、一人でも20、30の敵にも負けないのである。まず、気持ちに兵法を忘れず、正しく一生懸命鍛錬すれば、まず手でも人に勝ち、見る目においても人に勝つことができる。 鍛錬の結果、体が自由自在になれば体でも人に勝ち、この道に心が慣れれば心でも人に勝つことができるのである。兵法を学んでこの境地にたどりついた時は、すべてにおいて人に負けることはありえない。また、集団の兵法では、有能な人を仲間に持つことで勝り、多くの人数を使うことに勝り、わが身を正すことで勝ち、国を治めることでも勝ち、民を養うことでも勝ち、世の秩序を保つことができる。何事においても人に負けないことを知って、身を助け名誉を守ることこそ、兵法の道である。
___________________
「空を道とし、道を空とみる。」
(意味)
ここでいう「道」とは、武士としての道を意味すると思われ、
「空」とは、「迷いのない心」「とらわれない心」の事。
つまり、「無欲、無心が事をなす」となります。
_________
「神仏を敬い、神仏に頼らず。」
(意味)
神仏に頼るのではなく、神仏の意にかなう心構え、
生活姿勢が大切。
__________
千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす。
_______________
武士といえば、常に死ができている者と自惚れているようだが、
そんなものは出家、女、百姓とて同様だ。
武士が他と異なるのは、兵法の心得があるという一点においてだけだ。
_____________
構えあって構えなし。
__________
打ち込む態勢をつくるのが先で、剣はそれに従うものだ
__________
勝負とは、敵を先手、先手と打ち負かしていくことであり、
構えるということは、敵の先手を待つ心にほかならない。
「構える」などという後手は邪道なのである。
____________
一生の間、欲心を思わず。
_________
平常の身体のこなし方を戦いのときの身のこなし方とし、
戦いのときの身のこなし方を平常と同じ身のこなし方とすること。
_____________
われ事において後悔せず。
_____________
Posted by アマミちゃん(野崎りの) at 01:55│Comments(0)
│尊敬する人物
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。