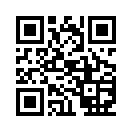五芒星の霊的な意味~エル・カンターレ・ファイトの潜在パワー
2011年09月01日
ちょっとばかし長いけど読んでおくと損はないぞよ。

五芒星 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
五芒星
使用例:ラウンドトップの窓に五芒星がデザインされた北炭滝之上水力発電所五芒星(ごぼうせい、英: Pentagram)または五芒星形・五角星形・五線星型・星型五角形・正5/2角形は、互いに交差する、長さの等しい5本の線分から構成される図形で星型正多角形の一種である。正五角形に内接し、対称的である。一筆書きが可能。五紡星と誤記されることがある。
5つの要素を並列的に図案化できる図形として、洋の東西を問わず使われてきた。世界中で魔術の記号とされ守護に用いることもあれば、上下を逆向きにして悪魔の象徴になることもある。悪魔の象徴としてとらえる際には、デビルスターと呼ばれることもある。また、外側の5つの三角形が星の光彩を連想させることから、星を表す記号としてよく用いられる。
内側に生じる小さな正五角形を取り除いた形(☆:五光星)もしばしば五芒星と呼ばれることがある。また、この「五光星」には「五稜星」(ごりょうせい)という別名もある。
幾何学的性質
描き方

五芒星を描く向きには、右上の図のように1角が上を向くようにする方法(しばしば「上向き」と呼ばれる)と、これを36度回転させて得られる、2角が上を向くようにする方法(しばしば「下向き」と呼ばれる)の2通りがよくみられる。いずれを用いるかは歴史的には一定していないが、近年では上向きのほうが多く用いられる。
また、描き順には文化的な意味が割り当てられている。
黄金比
図において、青の線分と赤の線分の長さの比、同じく緑と青の比、紫と緑の比は一定の値 を取る。これは黄金比と等しい。
古くから黄金比で構成されている図形は美しいとされており、単純ながらも黄金比を数多く含む五芒星は美しい図形の代表格とされた。
陰陽道と安倍晴明の桔梗印
五芒星は、陰陽道では魔除けの呪符として伝えられている。印にこめられたその意味は、陰陽道の基本概念となった陰陽五行説、木・火・土・金・水の5つの元素の働きの相克を表したものであり、五芒星はあらゆる魔除けの呪符として重宝された。
日本の平安時代の陰陽師、安倍晴明は五行の象徴として、五芒星の紋を用いた。「安倍清明判(あべのせいめいばん)」や「清明九字(せいめいくじ)」とも言い、キキョウの花を図案化した桔梗紋の変形として、「晴明桔梗(せいめいききょう)」とも言う。家紋として現在使用されているものの多くは、桔梗紋の清明桔梗と見られ、現在も晴明神社の神紋などに見ることができる(セーマンドーマンも参照)。
大日本帝国陸軍

明治最初期から昭和の太平洋戦争直前まで、帝国陸軍の将校准士官が正装・礼装時に着用する正衣(大礼服)の正帽の天井には、金線(銀線)で五芒星が刺繍されていた。「陸軍服制」(明治33年勅令第364号)によると、大将から兵卒まで、帝国陸軍の軍帽には五芒星が刺繍されていた。桜花の萼(がく)の形を模しているとも、弾除け(多魔除け)の意味をかついで採用されていたとも言われており、その起源や意味についてははっきりしない。
また陸軍軍属においても、親任官以下全ての陸軍軍属が着用する軍属従軍服(軍属服)では、五芒星を模した臂章が制式(昭和18年制)であった他、平服着用時に佩用するバッジ型(七宝焼き)の徽章でも五芒星が使われていた。
古代西洋
歴史的に確認されているもっとも古い五芒星の用法は、紀元前3000年頃のメソポタミアの書物である。シュメール人はこれをUB(ウブ)と呼んだ。さらに下向き五芒星を「角・小さな空間・穴」などの意味を表す絵文字とする。エジプトでは子宮を表させていたことから性的意味合いがあるとも言われている。バビロニアでは、図形の各側面に前後左右と上の各方向を割り当て、それぞれ木星・水星・火星・土星、そして上に地母神イシュタルの現れとされた金星を対応させた。五芒星に五惑星を対応させる考え方は、後のヨーロッパにも見受けられる。
また、火・水・風・土の四大元素に霊を加えた5つのエレメントにもそれぞれの頂点が対応させられ、それは現在でも魔法などのシンボリズムに使われている。

五行思想出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
五行思想(ごぎょうしそう)または五行説(ごぎょうせつ)とは、古代中国に端を発する自然哲学の思想で、万物は木・火・土・金・水の5種類の元素からなるという説である。
また、5種類の元素は『互いに影響を与え合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する』という考えが根底に存在する。
西洋の四大元素説(四元素説)と比較される思想である。
起源
五行思想は、戦国時代の陰陽家騶衍(すうえん。騶は{馬芻}。鄒衍と表記する場合もある,紀元前305年頃 - 紀元前240年頃)が理論づけたとされる。
一説によると、元素を5つとしたのは、当時中国では5つの惑星が観測されていたためだという。少なくとも当時から知られていた惑星、水星・金星・火星・木星・土星の名称は五行に対応している。
春秋戦国時代の末頃に陰陽思想と一体で扱われるようになり、陰陽五行説となった。
五行
木(木行)
木の花や葉が幹の上を覆っている立木が元となっていて、樹木の成長・発育する様子を表す。「春」の象徴。
火(火行)
光り煇く炎が元となっていて、火のような灼熱の性質を表す。「夏」の象徴。
土(土行)
植物の芽が地中から発芽する様子が元となっていて、万物を育成・保護する性質を表す。「季節の変わり目」の象徴。
金(金行)
土中に光り煇く鉱物・金属が元となっていて、金属のように冷徹・堅固・確実な性質を表す。収獲の季節「秋」の象徴。
水(水行)
泉から涌き出て流れる水が元となっていて、これを命の泉と考え、胎内と霊性を兼ね備える性質を表す。「冬」の象徴。
四季の変化は五行の推移によって起こると考えられた。また、方角・色など、あらゆる物に五行が配当されている。そこから、四季に対応する五行の色と四季を合わせて、青春、朱夏、白秋、玄冬といった言葉が生まれた。詩人、北原白秋の雅号は秋の白秋にちなんだものである。
五行 木 火 土 金 水
五色 青(緑) 紅 黄 白 玄(黒)
五方 東 南 中 西 北
五時 春 夏 土用 秋 冬
節句 人日 上巳 端午 七夕 重陽
五星 歳星(木星) 螢惑(火星) 填星(土星) 太白(金星) 辰星(水星)
五音 角 徴 宮 商 羽
五声 呼 言 歌 哭 呻
五臓 肝 心(心包) 脾 肺 腎
五情 喜 楽 怨 怒 哀
五志 怒 喜・笑 思・慮(考) 悲・憂 恐・驚
五腑 胆 小腸(三焦) 胃 大腸 膀胱
五指 薬指 中指 人差指 親指 小指
五官 目 舌 口 鼻 耳
五液 涙 汗 涎 涕 唾
五塵 色(視覚) 触(触覚) 味(味覚) 香(嗅覚) 声(聴覚)
五味 酸 苦 甘 辛 鹹(塩辛さ)
五味の走る所 筋 骨 営・智 気 精
五禁 辛 鹹(塩辛さ) 苦 甘 酸
五主 筋・爪 血脈 肌肉・唇 皮毛 骨髄・髪
五事 貌 視 思 言 聴
五虫 鱗(魚と爬虫類) 羽(鳥) 裸(ヒト) 毛(獣) 介(カメ、甲殻類と貝類)
五獣 青竜 朱雀 黄麟や黄竜 白虎 玄武
五竜 青竜 赤竜 黄竜 白竜 黒竜
五麟 聳孤(しょうこ) 炎駒(えんく) 麒麟(きりん) 索冥(さくめい) 角端(かくたん)
五畜 犬 羊 牛 鶏 猪
五果 李 杏 棗 桃 栗
五穀 麻・胡麻 麦 米 黍 大豆
五菜 韭 薤 葵 葱 藿(カク:豆の葉)
五常(五徳) 仁 礼 信 義 智
五悪 風 熱・暑 湿 燥・寒 寒・燥
五変 握 憂 噦 欬 慄
五金 錫(青金) 銅(赤金) 金(黄金) 銀(白金) 鉄(黒金)
十干 甲・乙 丙・丁 戊・己 庚・辛 壬・癸
十二支 寅・卯 巳・午 辰・未・戌・丑 申・酉 亥・子
月(旧暦) 1 - 3月 4 - 6月 (割当なし) 7 - 9月 10 - 12月
五行の生成とその順序
五行説と陰陽説が統合されて陰陽五行説が成立した段階で、五行が混沌から太極を経て生み出されたという考え方が成立して、五行の生成とその順序が確立した。
1.太極が陰陽に分離し、陰の中で特に冷たい部分が北に移動して水行を生じ、
2.次いで陽の中で特に熱い部分が南へ移動して火行を生じた。
3.さらに残った陽気は東に移動し風となって散って木行を生じ、
4.残った陰気が西に移動して金行を生じた。
5.そして四方の各行から余った気が中央に集まって土行が生じた。
というのが五行の生成順序である。
そのため五行に数を当てはめる場合五行の生成順序に従って、水行は生数が1で成数が6、火行は生数が2で成数が7、木行は生数が3で成数が8、金行は生数が4で成数が9、土行は生数が5で成数が10、となる。
なお木行が風から生まれたとされる部分には四大説の影響が見られる。
五行の関係
五行の互いの関係には、「相生」「相剋(相克)」「比和」「相乗」「相侮」という性質が付与されている。
相生
順送りに相手を生み出して行く、陽の関係。
木生火
木は燃えて火を生む。
火生土
物が燃えればあとには灰が残り、灰は土に還る。
土生金
鉱物・金属の多くは土の中にあり、土を掘ることによってその金属を得ることができる。
金生水
金属の表面には凝結により水が生じる。
水生木
木は水によって養われ、水がなければ木は枯れてしまう。
相剋
相手を打ち滅ぼして行く、陰の関係。
木剋土
木は根を地中に張って土を締め付け、養分を吸い取って土地を痩せさせる。
土剋水
土は水を濁す。また、土は水を吸い取り、常にあふれようとする水を堤防や土塁等でせき止める。
水剋火
水は火を消し止める。
火剋金
火は金属を熔かす。
金剋木
金属製の斧や鋸は木を傷つけ、切り倒す。
元々は「相勝」だったが、「相生」と音が重なってしまうため、「相克」⇒「相剋」となった。「克」には戦って勝つという意味がある。「剋」は「克」にある戦いの意味を強調するために刃物である「刂」を「克」に付加した文字である。同様に克に武器を意味する「寸」を加えた尅を使うこともある。
比和
同じ気が重なると、その気は盛んになる。その結果が良い場合にはますます良く、悪い場合にはますます悪くなる。
相侮
侮とは侮る、相剋の反対で、反剋する関係にある。
木侮金
木が強すぎると、金の克制を受け付けず、逆に木が金を侮る
金侮火
金が強すぎると、火の克制を受け付けず、逆に金が火を侮る
火侮水
火が強すぎると、水の克制を受け付けず、逆に火が水を侮る
水侮土
水が強すぎると、土の克制を受け付けず、逆に水が土を侮る
土侮木
土が強すぎると、木の克制を受け付けず、逆に土が木を侮る
火虚金侮
火自身が弱いため、金を克制することができず、逆に金が火を侮る
水虚火侮
水自身が弱いため、火を克制することができず、逆に火が水を侮る
土虚水侮
土自身が弱いため、水を克制することができず、逆に水が土を侮る
木虚土侮
木自身が弱いため、土を克制することができず、逆に土が木を侮る
金虚木侮
金自身が弱いため、木を克制することができず、逆に木が金を侮る
相乗
乗とは陵辱する、相剋が度を過ぎて過剰になったもの。
木乗土
木が強すぎて、土を克し過ぎ、土の形成が不足する。
土乗水
土が強すぎて、水を克し過ぎ、水を過剰に吸収する。
水乗火
水が強すぎて、火を克し過ぎ、火を完全に消火する。
火乗金
火が強すぎて、金を克し過ぎ、金を完全に熔解する。
金乗木
金が強すぎて、木を克し過ぎ、木を完全に切り倒す。
土虚木乗
土自身が弱いため、木剋土の力が相対的に強まって、土がさらに弱められること。
水虚土乗
水自身が弱いため、土剋水の力が相対的に強まって、水がさらに弱められること。
火虚水乗
火自身が弱いため、水剋火の力が相対的に強まって、火がさらに弱められること。
金虚火乗
金自身が弱いため、火剋金の力が相対的に強まって、金がさらに弱められること。
木虚金乗
木自身が弱いため、金剋木の力が相対的に強まって、木がさらに弱められること。
相剋と相生
相剋の中にも相生があると言える。例えば、土は木の根が張ることでその流出を防ぐことができる。水は土に流れを抑えられることで、谷や川の形を保つことができる。金は火に熔かされることで、刀や鋸などの金属製品となり、木は刃物によって切られることで様々な木工製品に加工される。火は水によって消されることで、一切を燃やし尽くさずにすむ。
逆に、相生の中にも相剋がある。木が燃え続ければ火はやがて衰え、水が溢れ続ければ木は腐ってしまい、金に水が凝結しすぎると金が錆び、土から鉱石を採りすぎると土がその分減り、物が燃えた時に出る灰が溜まり過ぎると土の処理能力が追いつかなくなる。
森羅万象の象徴である五気の間には、相生・相剋の2つの面があって初めて穏当な循環が得られ、五行の循環によって宇宙の永遠性が保証される。
なお、相生相剋には主体客体の別があるため、自らが他を生み出すことを「洩(泄)」、自らが他から生じられることを「生」、自らが他を剋すことを「分」、自らが他から剋されることを「剋」と細かく区別することがある。
日本神話における五行
日本神話においては、水徳の神が国狭槌尊、火徳の神が豊斟渟尊、木徳の神が泥土瓊尊・沙土瓊尊、金徳の神が大戸之道尊・大苫辺尊、土徳の神が面足尊・惶根尊とされる(神皇正統記の記述より)。
金星が描くペンタクル
ベストセラー小説である「ダ・ヴィンチ・コード」(ダン・ブラウン著)の中に、「黄金比」や金星が軌道上に描く五芒星(ごぼうせい:Pentacle)が出てきます。
黄金比、金星の描く五芒星とは一体どのようなものでしょうか?
★黄金比 φ=1.618…
レオナルド・フィボナッチ(1170-1250年)の算術書に現れる"フィボナッチ数列"は隣接する2つの数字の和が次の項になるような数列です。
1、1、2、3、5、8、13、21、・・・
フィボナッチ数列の隣接する2つの数字の比は数字が大きくなるにしたがい、黄金比φに近づいていきます。
黄金比φは次の式で表されます。
φ=1+1/φ もしくは φ=1/(φ-1)
これを解いて、φ=1.618・・・
黄金比は自然界のいろいろなところに隠れていると言われています。また、調和や秩序を生み出す、最も美しい数字、と考えている人もいます。
★五芒星と黄金比
正五角形の角を結んでできる五芒星には黄金比が隠れています(右図)。
a:b = 1:φ (黄金比!)
b:c = 1:φ (黄金比!)

★金星が描く五芒星
金星は地球より早く軌道を巡り、1.6年ごとに地球を追い抜かします("会合")。
金星公転周期 = 0.615年
地球公転周期 = 1.0年(=金星公転周期の1.6倍:ほぼ黄金比!)
会合周期 = 1.6年(=地球公転周期の1.6倍:ほぼ黄金比!)
したがって、金星は8年間に5回地球と会合し、会合場所を順番に線で結んでいくと軌道上に五芒星を描くことになります(下図)。

金星Venusは美の女神の名前です。古代の人々にとって、黄金比を宿す金星はまさに美の象徴であったのです。

五芒星 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
五芒星
使用例:ラウンドトップの窓に五芒星がデザインされた北炭滝之上水力発電所五芒星(ごぼうせい、英: Pentagram)または五芒星形・五角星形・五線星型・星型五角形・正5/2角形は、互いに交差する、長さの等しい5本の線分から構成される図形で星型正多角形の一種である。正五角形に内接し、対称的である。一筆書きが可能。五紡星と誤記されることがある。
5つの要素を並列的に図案化できる図形として、洋の東西を問わず使われてきた。世界中で魔術の記号とされ守護に用いることもあれば、上下を逆向きにして悪魔の象徴になることもある。悪魔の象徴としてとらえる際には、デビルスターと呼ばれることもある。また、外側の5つの三角形が星の光彩を連想させることから、星を表す記号としてよく用いられる。
内側に生じる小さな正五角形を取り除いた形(☆:五光星)もしばしば五芒星と呼ばれることがある。また、この「五光星」には「五稜星」(ごりょうせい)という別名もある。
幾何学的性質
描き方

五芒星を描く向きには、右上の図のように1角が上を向くようにする方法(しばしば「上向き」と呼ばれる)と、これを36度回転させて得られる、2角が上を向くようにする方法(しばしば「下向き」と呼ばれる)の2通りがよくみられる。いずれを用いるかは歴史的には一定していないが、近年では上向きのほうが多く用いられる。
また、描き順には文化的な意味が割り当てられている。
黄金比
図において、青の線分と赤の線分の長さの比、同じく緑と青の比、紫と緑の比は一定の値 を取る。これは黄金比と等しい。
古くから黄金比で構成されている図形は美しいとされており、単純ながらも黄金比を数多く含む五芒星は美しい図形の代表格とされた。
陰陽道と安倍晴明の桔梗印
五芒星は、陰陽道では魔除けの呪符として伝えられている。印にこめられたその意味は、陰陽道の基本概念となった陰陽五行説、木・火・土・金・水の5つの元素の働きの相克を表したものであり、五芒星はあらゆる魔除けの呪符として重宝された。
日本の平安時代の陰陽師、安倍晴明は五行の象徴として、五芒星の紋を用いた。「安倍清明判(あべのせいめいばん)」や「清明九字(せいめいくじ)」とも言い、キキョウの花を図案化した桔梗紋の変形として、「晴明桔梗(せいめいききょう)」とも言う。家紋として現在使用されているものの多くは、桔梗紋の清明桔梗と見られ、現在も晴明神社の神紋などに見ることができる(セーマンドーマンも参照)。
大日本帝国陸軍

明治最初期から昭和の太平洋戦争直前まで、帝国陸軍の将校准士官が正装・礼装時に着用する正衣(大礼服)の正帽の天井には、金線(銀線)で五芒星が刺繍されていた。「陸軍服制」(明治33年勅令第364号)によると、大将から兵卒まで、帝国陸軍の軍帽には五芒星が刺繍されていた。桜花の萼(がく)の形を模しているとも、弾除け(多魔除け)の意味をかついで採用されていたとも言われており、その起源や意味についてははっきりしない。
また陸軍軍属においても、親任官以下全ての陸軍軍属が着用する軍属従軍服(軍属服)では、五芒星を模した臂章が制式(昭和18年制)であった他、平服着用時に佩用するバッジ型(七宝焼き)の徽章でも五芒星が使われていた。
古代西洋
歴史的に確認されているもっとも古い五芒星の用法は、紀元前3000年頃のメソポタミアの書物である。シュメール人はこれをUB(ウブ)と呼んだ。さらに下向き五芒星を「角・小さな空間・穴」などの意味を表す絵文字とする。エジプトでは子宮を表させていたことから性的意味合いがあるとも言われている。バビロニアでは、図形の各側面に前後左右と上の各方向を割り当て、それぞれ木星・水星・火星・土星、そして上に地母神イシュタルの現れとされた金星を対応させた。五芒星に五惑星を対応させる考え方は、後のヨーロッパにも見受けられる。
また、火・水・風・土の四大元素に霊を加えた5つのエレメントにもそれぞれの頂点が対応させられ、それは現在でも魔法などのシンボリズムに使われている。

五行思想出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
五行思想(ごぎょうしそう)または五行説(ごぎょうせつ)とは、古代中国に端を発する自然哲学の思想で、万物は木・火・土・金・水の5種類の元素からなるという説である。
また、5種類の元素は『互いに影響を与え合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する』という考えが根底に存在する。
西洋の四大元素説(四元素説)と比較される思想である。
起源
五行思想は、戦国時代の陰陽家騶衍(すうえん。騶は{馬芻}。鄒衍と表記する場合もある,紀元前305年頃 - 紀元前240年頃)が理論づけたとされる。
一説によると、元素を5つとしたのは、当時中国では5つの惑星が観測されていたためだという。少なくとも当時から知られていた惑星、水星・金星・火星・木星・土星の名称は五行に対応している。
春秋戦国時代の末頃に陰陽思想と一体で扱われるようになり、陰陽五行説となった。
五行
木(木行)
木の花や葉が幹の上を覆っている立木が元となっていて、樹木の成長・発育する様子を表す。「春」の象徴。
火(火行)
光り煇く炎が元となっていて、火のような灼熱の性質を表す。「夏」の象徴。
土(土行)
植物の芽が地中から発芽する様子が元となっていて、万物を育成・保護する性質を表す。「季節の変わり目」の象徴。
金(金行)
土中に光り煇く鉱物・金属が元となっていて、金属のように冷徹・堅固・確実な性質を表す。収獲の季節「秋」の象徴。
水(水行)
泉から涌き出て流れる水が元となっていて、これを命の泉と考え、胎内と霊性を兼ね備える性質を表す。「冬」の象徴。
四季の変化は五行の推移によって起こると考えられた。また、方角・色など、あらゆる物に五行が配当されている。そこから、四季に対応する五行の色と四季を合わせて、青春、朱夏、白秋、玄冬といった言葉が生まれた。詩人、北原白秋の雅号は秋の白秋にちなんだものである。
五行 木 火 土 金 水
五色 青(緑) 紅 黄 白 玄(黒)
五方 東 南 中 西 北
五時 春 夏 土用 秋 冬
節句 人日 上巳 端午 七夕 重陽
五星 歳星(木星) 螢惑(火星) 填星(土星) 太白(金星) 辰星(水星)
五音 角 徴 宮 商 羽
五声 呼 言 歌 哭 呻
五臓 肝 心(心包) 脾 肺 腎
五情 喜 楽 怨 怒 哀
五志 怒 喜・笑 思・慮(考) 悲・憂 恐・驚
五腑 胆 小腸(三焦) 胃 大腸 膀胱
五指 薬指 中指 人差指 親指 小指
五官 目 舌 口 鼻 耳
五液 涙 汗 涎 涕 唾
五塵 色(視覚) 触(触覚) 味(味覚) 香(嗅覚) 声(聴覚)
五味 酸 苦 甘 辛 鹹(塩辛さ)
五味の走る所 筋 骨 営・智 気 精
五禁 辛 鹹(塩辛さ) 苦 甘 酸
五主 筋・爪 血脈 肌肉・唇 皮毛 骨髄・髪
五事 貌 視 思 言 聴
五虫 鱗(魚と爬虫類) 羽(鳥) 裸(ヒト) 毛(獣) 介(カメ、甲殻類と貝類)
五獣 青竜 朱雀 黄麟や黄竜 白虎 玄武
五竜 青竜 赤竜 黄竜 白竜 黒竜
五麟 聳孤(しょうこ) 炎駒(えんく) 麒麟(きりん) 索冥(さくめい) 角端(かくたん)
五畜 犬 羊 牛 鶏 猪
五果 李 杏 棗 桃 栗
五穀 麻・胡麻 麦 米 黍 大豆
五菜 韭 薤 葵 葱 藿(カク:豆の葉)
五常(五徳) 仁 礼 信 義 智
五悪 風 熱・暑 湿 燥・寒 寒・燥
五変 握 憂 噦 欬 慄
五金 錫(青金) 銅(赤金) 金(黄金) 銀(白金) 鉄(黒金)
十干 甲・乙 丙・丁 戊・己 庚・辛 壬・癸
十二支 寅・卯 巳・午 辰・未・戌・丑 申・酉 亥・子
月(旧暦) 1 - 3月 4 - 6月 (割当なし) 7 - 9月 10 - 12月
五行の生成とその順序
五行説と陰陽説が統合されて陰陽五行説が成立した段階で、五行が混沌から太極を経て生み出されたという考え方が成立して、五行の生成とその順序が確立した。
1.太極が陰陽に分離し、陰の中で特に冷たい部分が北に移動して水行を生じ、
2.次いで陽の中で特に熱い部分が南へ移動して火行を生じた。
3.さらに残った陽気は東に移動し風となって散って木行を生じ、
4.残った陰気が西に移動して金行を生じた。
5.そして四方の各行から余った気が中央に集まって土行が生じた。
というのが五行の生成順序である。
そのため五行に数を当てはめる場合五行の生成順序に従って、水行は生数が1で成数が6、火行は生数が2で成数が7、木行は生数が3で成数が8、金行は生数が4で成数が9、土行は生数が5で成数が10、となる。
なお木行が風から生まれたとされる部分には四大説の影響が見られる。
五行の関係
五行の互いの関係には、「相生」「相剋(相克)」「比和」「相乗」「相侮」という性質が付与されている。
相生
順送りに相手を生み出して行く、陽の関係。
木生火
木は燃えて火を生む。
火生土
物が燃えればあとには灰が残り、灰は土に還る。
土生金
鉱物・金属の多くは土の中にあり、土を掘ることによってその金属を得ることができる。
金生水
金属の表面には凝結により水が生じる。
水生木
木は水によって養われ、水がなければ木は枯れてしまう。
相剋
相手を打ち滅ぼして行く、陰の関係。
木剋土
木は根を地中に張って土を締め付け、養分を吸い取って土地を痩せさせる。
土剋水
土は水を濁す。また、土は水を吸い取り、常にあふれようとする水を堤防や土塁等でせき止める。
水剋火
水は火を消し止める。
火剋金
火は金属を熔かす。
金剋木
金属製の斧や鋸は木を傷つけ、切り倒す。
元々は「相勝」だったが、「相生」と音が重なってしまうため、「相克」⇒「相剋」となった。「克」には戦って勝つという意味がある。「剋」は「克」にある戦いの意味を強調するために刃物である「刂」を「克」に付加した文字である。同様に克に武器を意味する「寸」を加えた尅を使うこともある。
比和
同じ気が重なると、その気は盛んになる。その結果が良い場合にはますます良く、悪い場合にはますます悪くなる。
相侮
侮とは侮る、相剋の反対で、反剋する関係にある。
木侮金
木が強すぎると、金の克制を受け付けず、逆に木が金を侮る
金侮火
金が強すぎると、火の克制を受け付けず、逆に金が火を侮る
火侮水
火が強すぎると、水の克制を受け付けず、逆に火が水を侮る
水侮土
水が強すぎると、土の克制を受け付けず、逆に水が土を侮る
土侮木
土が強すぎると、木の克制を受け付けず、逆に土が木を侮る
火虚金侮
火自身が弱いため、金を克制することができず、逆に金が火を侮る
水虚火侮
水自身が弱いため、火を克制することができず、逆に火が水を侮る
土虚水侮
土自身が弱いため、水を克制することができず、逆に水が土を侮る
木虚土侮
木自身が弱いため、土を克制することができず、逆に土が木を侮る
金虚木侮
金自身が弱いため、木を克制することができず、逆に木が金を侮る
相乗
乗とは陵辱する、相剋が度を過ぎて過剰になったもの。
木乗土
木が強すぎて、土を克し過ぎ、土の形成が不足する。
土乗水
土が強すぎて、水を克し過ぎ、水を過剰に吸収する。
水乗火
水が強すぎて、火を克し過ぎ、火を完全に消火する。
火乗金
火が強すぎて、金を克し過ぎ、金を完全に熔解する。
金乗木
金が強すぎて、木を克し過ぎ、木を完全に切り倒す。
土虚木乗
土自身が弱いため、木剋土の力が相対的に強まって、土がさらに弱められること。
水虚土乗
水自身が弱いため、土剋水の力が相対的に強まって、水がさらに弱められること。
火虚水乗
火自身が弱いため、水剋火の力が相対的に強まって、火がさらに弱められること。
金虚火乗
金自身が弱いため、火剋金の力が相対的に強まって、金がさらに弱められること。
木虚金乗
木自身が弱いため、金剋木の力が相対的に強まって、木がさらに弱められること。
相剋と相生
相剋の中にも相生があると言える。例えば、土は木の根が張ることでその流出を防ぐことができる。水は土に流れを抑えられることで、谷や川の形を保つことができる。金は火に熔かされることで、刀や鋸などの金属製品となり、木は刃物によって切られることで様々な木工製品に加工される。火は水によって消されることで、一切を燃やし尽くさずにすむ。
逆に、相生の中にも相剋がある。木が燃え続ければ火はやがて衰え、水が溢れ続ければ木は腐ってしまい、金に水が凝結しすぎると金が錆び、土から鉱石を採りすぎると土がその分減り、物が燃えた時に出る灰が溜まり過ぎると土の処理能力が追いつかなくなる。
森羅万象の象徴である五気の間には、相生・相剋の2つの面があって初めて穏当な循環が得られ、五行の循環によって宇宙の永遠性が保証される。
なお、相生相剋には主体客体の別があるため、自らが他を生み出すことを「洩(泄)」、自らが他から生じられることを「生」、自らが他を剋すことを「分」、自らが他から剋されることを「剋」と細かく区別することがある。
日本神話における五行
日本神話においては、水徳の神が国狭槌尊、火徳の神が豊斟渟尊、木徳の神が泥土瓊尊・沙土瓊尊、金徳の神が大戸之道尊・大苫辺尊、土徳の神が面足尊・惶根尊とされる(神皇正統記の記述より)。
金星が描くペンタクル
ベストセラー小説である「ダ・ヴィンチ・コード」(ダン・ブラウン著)の中に、「黄金比」や金星が軌道上に描く五芒星(ごぼうせい:Pentacle)が出てきます。
黄金比、金星の描く五芒星とは一体どのようなものでしょうか?
★黄金比 φ=1.618…
レオナルド・フィボナッチ(1170-1250年)の算術書に現れる"フィボナッチ数列"は隣接する2つの数字の和が次の項になるような数列です。
1、1、2、3、5、8、13、21、・・・
フィボナッチ数列の隣接する2つの数字の比は数字が大きくなるにしたがい、黄金比φに近づいていきます。
黄金比φは次の式で表されます。
φ=1+1/φ もしくは φ=1/(φ-1)
これを解いて、φ=1.618・・・
黄金比は自然界のいろいろなところに隠れていると言われています。また、調和や秩序を生み出す、最も美しい数字、と考えている人もいます。
★五芒星と黄金比
正五角形の角を結んでできる五芒星には黄金比が隠れています(右図)。
a:b = 1:φ (黄金比!)
b:c = 1:φ (黄金比!)

★金星が描く五芒星
金星は地球より早く軌道を巡り、1.6年ごとに地球を追い抜かします("会合")。
金星公転周期 = 0.615年
地球公転周期 = 1.0年(=金星公転周期の1.6倍:ほぼ黄金比!)
会合周期 = 1.6年(=地球公転周期の1.6倍:ほぼ黄金比!)
したがって、金星は8年間に5回地球と会合し、会合場所を順番に線で結んでいくと軌道上に五芒星を描くことになります(下図)。

金星Venusは美の女神の名前です。古代の人々にとって、黄金比を宿す金星はまさに美の象徴であったのです。
天使の臨在
奄美雛形説、順調に広がってる件
寝言4
【千葉さんより】エル・カンターレと神道を結ぶ女神の秘密
なぜ奄美の神が幸福の科学を選んだのか、アマミちゃん3つの仮説
見抜かれることを恐れるモノ(師匠話限定復活)
奄美雛形説、順調に広がってる件
寝言4
【千葉さんより】エル・カンターレと神道を結ぶ女神の秘密
なぜ奄美の神が幸福の科学を選んだのか、アマミちゃん3つの仮説
見抜かれることを恐れるモノ(師匠話限定復活)
Posted by アマミちゃん(野崎りの) at 09:26│Comments(7)
│幸福の科学スピリチュアルエピソード
この記事へのコメント
すごいですね!金星の護りだ!と思いました。
五ぼう星の書き順が何気に気になってたんで、納得!
フィポナッチ数列はダヴィンチコードでお馴染みになってますが、さっぱりわからない系かも・・数学、幾何は嫌いじゃないんだけどなぁ。
ピタゴラスもある種の秘儀教団だったようで、書籍の「フェルマーの最終定理」に出てきます。
軍服の五ぼう星もエレガント!護符を知ってた方のデザインに違いない!
ますます神道によるこの国の護りのすごさ、感じ入ります。
これ知らないのもったいないのにな・・。
五ぼう星の書き順が何気に気になってたんで、納得!
フィポナッチ数列はダヴィンチコードでお馴染みになってますが、さっぱりわからない系かも・・数学、幾何は嫌いじゃないんだけどなぁ。
ピタゴラスもある種の秘儀教団だったようで、書籍の「フェルマーの最終定理」に出てきます。
軍服の五ぼう星もエレガント!護符を知ってた方のデザインに違いない!
ますます神道によるこの国の護りのすごさ、感じ入ります。
これ知らないのもったいないのにな・・。
Posted by きんぎょ at 2011年09月01日 10:57
非常に参考になります。
有難うございました。
有難うございました。
Posted by ゆかりん at 2011年09月01日 10:59
こちら西洋の五芒星の儀式
開封の描き順があるようで・・・しだいに呪術的になってくるので
人間修行から逸れて行かぬよう・・・☆
開封の描き順があるようで・・・しだいに呪術的になってくるので
人間修行から逸れて行かぬよう・・・☆
Posted by vega_talk at 2011年09月01日 12:40
こちらで立体の 五ぼう星★
スターケージ ♯5(プレアデス) 日詰明男
組み立てが難しく、ことごとく失敗するようです。
私は 完成品を 天井からブルさげてます。☆
スターケージ ♯5(プレアデス) 日詰明男
組み立てが難しく、ことごとく失敗するようです。
私は 完成品を 天井からブルさげてます。☆
Posted by vega_talk at 2011年09月01日 12:49
携帯から見れなかった。残念です。
Posted by ぶどうぐみ at 2011年09月01日 15:13
ほえ~~~~・・・・
知りたいことが全部書いてありました
大変参考になりました!
ありがとうございました
ほえ・・・・・・・
知りたいことが全部書いてありました
大変参考になりました!
ありがとうございました
ほえ・・・・・・・
Posted by キラリ at 2011年09月01日 22:55
こういう呪術的な意匠や模様のお話大好きです。
神秘的ですし、浪漫がありますよね。
不可思議な神聖幾何学とでもいうのでしょうか。
私が興味があるのは、西洋では「フラワーオブライフ」
日本では「麻の葉文様」です。
アマミさんのご意見を拝聴したく思います。
神秘的ですし、浪漫がありますよね。
不可思議な神聖幾何学とでもいうのでしょうか。
私が興味があるのは、西洋では「フラワーオブライフ」
日本では「麻の葉文様」です。
アマミさんのご意見を拝聴したく思います。
Posted by iio at 2011年09月07日 07:40
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。